引越し準備はいつから始めればいいのか、漏れなく効率よく引越したいと悩む方も多いでしょう。
結論、きちんと準備ができていれば、引越し直前に慌てることもなくスムーズな引越しが可能です。
そこで、今回は引越しの準備について以下の要点を中心にご紹介します。
- 引越し1ヶ月前にやること
- 引越し2週間前にやること
- 引越し1週間前から前日までにやること
- 引越し後にやること
あらかじめ、どのタイミングで何をしなければいけないのか、時系列に沿って紹介していきます。
効率的に引越しするには、しっかりとスケジュールを立て、やるべきことをリスト化することが重要です。
忙しくて荷造りまで手が回らないという方も、荷造りから対応してくれるサービスもあるので、安心してくださいね。
中でもおすすめなのは、サカイ引越センターの「荷造りお任せパック」です。
荷造りお任せパックとは、荷造りから荷ほどき、新居の掃除まで専門スタッフが行ってくれるサービスとなります。
サカイ引越センターの公式サイトから簡単に見積もりが取れるので、ぜひ利用してみてください。
サカイ引越センター以外の引越業者と、料金やサービスを比較するなら見積もりサイトが便利!
希望の条件を入力するだけで、まとめて複数の業者に引越しの見積もりを依頼できます。
なかでも、口コミ数の多い「引越し侍」が参考になるのでおすすめです。
引越しの見積もりサイトを比較した、以下の表をぜひ活用してください。
横にスクロールします
| 見積もりサイト | 
引越し侍 |

くらしのマーケット |

DOOR引越し見積もり |

引越しラクっとNAVI |
|---|---|---|---|---|
| おすすめな人 | 大手引越し業者も含めて料金比較をしたい人 |
別の引越し作業も合わせて依頼したい人 |
赤帽の料金も含めて比較したい人 |
業者とのやり取りを代行してほしい人 |
| 提携業者数 | 340社〜 | 590社〜 | 130社〜 | 60社〜 |
| 依頼業者の選択 | 可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
| 電話番号入力 | 必須 |
必須 |
必須 |
必須 |
| 口コミ件数 | 80,000件〜 | 非公開 | 16件 | 50件〜 |
| 公式サイト | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
引越し準備はいつからやるべき?やることの流れや段取り
引越し準備は、基本的に引越しの1ヶ月前から行いましょう。
引越し当日までの大まかな流れは以下の通りです。
- 引越しが決まったら、新居探しや退去手続きを行なう
- 引越し1ヶ月前までに引越し業者の手配をする
- 粗大ゴミの処分や使用頻度が低いものの荷造り
- 電話やネット回線、公共料金の手続き
- 引越し2週間前に転出や転居手続き、印鑑登録の廃止手続き
- 引越し前日までに冷蔵庫や洗濯機の水抜き、荷物の最終チェック
引越しをスムーズに行なうためには、しっかりとした準備や計画が大切です。
引越し当日までの流れを把握し、やるべきことをリストアップしておきましょう。
引越しの準備でやるべきことは、
- 「引越し前にやること」
- 「引越し当日にやること」
- 「引越し後にやること」
と大きく3つに分かれます。
また、引越し準備も役所でしかできないこともあるため、いつまでにどのような手続きをしなければいけないのか確認しておきましょう。
以下のポイントを押さえておくと、やり忘れやトラブルを防ぐことができます。
- 引越しやることチェックリストPDFを印刷して準備する
- 見積もりなど業者への依頼は期日を明確にする
- 引越したらやるべき旧居・新居の掃除!
それぞれ詳しく紹介します。
引越しやることチェックリストPDFを印刷して準備する
いざ引越しを始めると、梱包資材の手配や住民票の手続きと、やらなければいけないことが多くあります。
やり忘れがないように、チェックリストを印刷して目に見えるところに置いておきましょう。
終わったものからチェックを付けて、進捗状況を見える化しておくのが重要です。
見える化することで、以下のようなメリットがあります。
- いつ、なにを、どのようにすればいいか一目でわかる
- 終わったものをチェックすることで達成感が味わえる
- 進捗状況を共有できる
また、家族で引越しをする場合は、役割分担を見える化するとスムーズに準備を進められます。
下記で当サイトオリジナルの、引越し準備やることチェックリストをPDFで印刷できるようにまとめました。
ぜひこちらを活用して、効率よく引越し準備を進めてくださいね!
【トラブル防止!】見積もりなど業者への依頼は期日を明確に
引越しには、様々なトラブルがあります。
中でも最も多いのは、「指定したはずの日時に業者が来ない」というものです。
このようなトラブルは、法律的に債務不履行にあたり業者の違法行為に該当します。
業者が引越し当日来ずに損害が出た場合は、業者に対して損害賠償を請求できるのです。
電話での「言った言ってない」問題は難しく、大きなトラブルに発展しかねないため、メールや見積もりの控えなどは必ず保管しておきましょう。
電話のみの依頼の場合は、担当者名や連絡日時などを記録しておく必要があります。
万が一トラブルに遭ってしまった場合は、国民生活センターに相談してみてください。
| 消費者ホットライン | 電話番号:188 (全国統一・通話料有料) |
|---|---|
| 平日バックアップ相談 | 電話番号:03-3446-1623 受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00 (年末年始、土日祝日除く) |
引越したらやるべき旧居・新居の掃除!
引越しの際は、旧居と新居の掃除をしましょう。
旧居の賃貸退去 掃除は特に必須で、退去費用が多く取られる可能性も。
退去費用を抑えるためにも、退去前に汚れがある場所がないか確認してください。
また新居でも清掃が行き届いていないことも考えられるので、荷物を入れる前に掃除することがおすすめです。
ほかにも、荷物がない状態でバルサンなど害虫の駆除や対策をしておくと安心。
使用する際は、火災報知機などに反応しないように気を付けましょう。
引越し1ヶ月前までにやることリスト|引越し先が決まったら準備すること
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 引越し先の情報を確認 | 全員 |
|
|
| 現住所の退去を管理会社に連絡 | 賃貸物件に住んでいる方 |
|
※退去連絡が遅れると家賃を二重に支払う可能性があるため |
| 現住所の駐車場の解約を管理会社に連絡 | 物件備え付けでない駐車場を借りている方 |
|
※連絡が遅れると翌月分の賃料を支払う可能性があるため |
| 引越し日を決める | 全員 | – | 引越し日によって料金が異なる 繁忙期や土日祝日は料金が高くなる場合がある |
| 引越しの見積もりを複数社取る | 全員 |
|
荷物量によって料金が変動する 事前に新居に運ぶ荷物を決めておく |
| 引越し業者を決定して依頼 | 全員 | – | 繁忙期の引越しを予定されている方は早めに予約を入れる |
| ダンボールなど梱包資材の受け取り | 全員 | – | 業者によって無料で提供される資材数は異なる 足りなくなった場合は、自前で用意する必要がある |
| 退去手続きの書類を提出 | 全員 | 解約申出書 | 事前に計画内容を確認し、提出期限に遅れないようにする |
| 学校の転校手続き | 別の市町村へ引越す方 |
|
引越しが決まったらできるだけ早めに学校に連絡する 高校生は編入試験が必要になる場合があるため、事前に確認しておく |
| 幼稚園・保育園の転園届の提出 | 別の市町村へ引越す方 | 在園証明書 | 引越しが決まったらできるだけ早めに学校に連絡する |
| 介護保険被保険者証の手続き | 別の市町村へ引越す方 | 介護保険被保険者証 | 引越し前の管轄役所で介護保険被保険者証を返納する 合わせて、資格喪失手続きを行う 介護保険受給資格証をもらう |
引越し日が決まったら、「いつ、なにを、どのように」するか計画を立てましょう。
引越し前日をゴールに設定して逆算し計画を立てると、スムーズに準備が進められます。
また、見積もり時には、新居に持っていくものと捨てるものが大まかに決めておくと良いでしょう。
1.引越し先の情報を確認
引越し先が決まったら、新居の下見をしておくのがおすすめです。
下見する際のチェックポイントは以下が挙げられます。
- 新居までの道順や新居前の道幅
- 部屋の間取りや広さ
- エレベーターの有無や大きさ、階段の幅
- ドアの高さや幅
- 窓のサイズ
事前に確かめておくと、家具家電の購入や荷物の搬入がスムーズに行えます。
スマートフォンなどで写真を撮っておくと便利です。
また、管理会社の問い合わせ先や初期費用がいくら必要なのかも確認しておきましょう。
2.現住居の退去を管理会社に連絡
賃貸物件にお住まいの方は、できるだけ早く管理会社に退去の連絡をしましょう。
引越し日が決まっていなくても、事前に退去の連絡をしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
賃貸契約の場合は、基本的に退去の1ヶ月前までに退去の連絡をしないと、家賃を二重に支払う可能性があるので注意しましょう。
退去の連絡は電話だけでなく書面でも行うと、管理会社との認識のズレがなくなるため、おすすめです。
3.現住居の駐車場の解約を管理会社に連絡
住居に備え付けでない月極駐車場を借りている場合は、管理会社に解約の連絡をしましょう。
基本的には引越しの1ヶ月前までに解約の連絡をするのが一般的です。
しかし、連絡が遅くなると余分に賃料を支払わなければならなくなります。
実際の解約日が解約の連絡をした月の翌月になる場合もあるため、事前に解約期限を確認しておきましょう。
4.引越し日を決める
引越し日はスケジュールを立てるためにも1ヶ月前には決めておく必要があります。
ただし、いつ引越すかによって料金に大きな差がでるため、少しでも費用を抑えたい方は安い時期を選ぶのがおすすめです。
とくに、3月から4月は繁忙期と呼ばれており、引越し料金が高くなる傾向があります。
横にスクロールします
| 人数 | 通常期 | 繁忙期 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 単身引越しの場合 | 45,511円 | 73,355円 | 27,844円 |
| 2人引越しの場合 | 76,884円 | 139,343円 | 62,459円 |
| 3人以上の引越しの場合 | 87,263円 | 174,171円 | 86,908円 |
繁忙期は単身引越しでも通常期の1.6倍、家族引越しでは2倍近く差が出ました。
引越しする時期を5月から2月にすると料金を安く抑えることができるでしょう。
また、家族で引越しされる場合は、平日と比べ土日祝日は料金が高くなります。
ある程度、引越し日を調整できる方は、土日祝日は避けて平日に引越すと費用が安くすむでしょう。
5.引越しの見積もりを複数社取る
引越し日が決まったら、複数の業者から見積もりを取りましょう。
自分で複数の業者に問い合わせる必要がない「一括見積もりサイト」がおすすめです。
一括見積もりサイトを利用すると以下のようなメリットがあります。
- 複数の業者から同時に見積もりが取れる
- 引越し費用の相場と最安値が把握できる
- 値引き交渉に有利
SUUMO引越し見積もりは、連絡先の入力が任意のため、セールスの電話がかかってくる心配がありません。
なかでも、取扱業者が業界トップの引越し侍は、数ある業者の中から最適な引越し業者 おすすめを見つけられます。
6.引越し業者を決定して依頼
引越し業者が決まったら、依頼の連絡をしましょう。
ただし、繁忙期である3月から4月は依頼が殺到するため、予約が取りにくくなることが考えられます。
繁忙期に引越しをする方はできるだけ早めに予約をしましょう。
また、通常期に引越しをされる方も早めに予約をすることで、希望日時の引越しができる可能性が高いです。
希望日に引越しをしたい方は、できるだけ早めに予約をしましょう。
7.ダンボールなど梱包資材の受け取り
引越し業者が決まったら、ダンボールなどの梱包資材が無料で提供されます。
ただし、提供される梱包資材には制限があり、プラン内容によっては有料になる場合があるため、見積もり時に確認しておくと良いでしょう。
無料で提供してもらえるダンボールの枚数は以下の通りです。
| 業者名 | ダンボール枚数 |
|---|---|
| サカイ引越センター | 最大50枚まで |
| ハート引越センター | 最大50枚まで |
| アリさんマークの引越社 | 最大50枚まで |
| アーク引越センター | 最大50枚まで |
| アート引越センター | 家族:最大50枚まで 単身:最大10枚まで |
| ベスト引越センター | 最大50枚まで |
ダンボールが足りなくなった場合は、自分で調達する必要があります。
主な入手先は以下が挙げられます。
- スーパーやコンビニドラッグストア
- ホームセンター
サカイ引越センターなら、ダンボールを自分で用意する手間がないのでおすすめです。
また、50枚も無料で提供してもらえるので安心してダンボールを利用できます。
忙しい引越しを少しでもスムーズに進めるために、サカイ引越センターを利用してみてくださいね。
8.退去手続きの書類を提出
管理会社に退去手続きの書類を提出します。
書類を提出して初めて退去手続きが完了したことになるため、退去1ヶ月前までには提出しましょう。
また、提出期限は契約内容によって異なる場合があるため、事前に賃貸契約書を確認する必要があります。
9.学校の転校手続き
子どもがいるご家庭は、学校の転校手続きが必要になります。
子どもが転校する学校によって、必要な手続きが異なるため注意しましょう。
手続きは引越しが決まったらなるべく早く行うのがおすすめです。
在学していた学校に転校する旨を伝え、以下2つを発行してもらいます。
- 在学証明書
- 教科書給与証明書
手続きの仕方や必要書類は転校する学校によって異なるため、事前に学校の窓口もしくは教育委員会に確認しておくと良いでしょう。
10.幼稚園・保育園の転園届の提出
子どもが幼稚園や保育園に在籍している場合は、転園届の提出が必要になります。
引越しが決まったらできる限り早く転園する旨を伝えましょう。
幼稚園や保育園の転園手続きは、地域や園によって違いがあるため、事前にしっかり確認しておくのが必要です。
最近では待機児童問題もあり、引越し先で幼稚園や保育園が見つけられない可能性もあります。
早めに引越し先での入園申し込みを済ませておくと良いでしょう。
11.介護保険被保険者証の手続き
要介護者が引越す場合は、役所で介護保険被保険者証の手続きが必要です。
他の市区町村へ引越す場合は、保険者証の返納と資格喪失手続きを行う必要があります。
同じ市区町村に引越す場合は、転居届を出すタイミングで手続きすると良いでしょう。
引越し2週間前までにやることリスト|荷造り準備や手続きなど
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 季節ものなどの 使う頻度が少ないものの荷造り |
全員 |
|
※玄関から遠い部屋の荷物から梱包する |
| 転出届の手続き | 他の市区町村に引っ越す方 |
|
旧住所にて行なう手続き 引越し日の14日前から手続き可能 |
| 電気 (現住所の解約と 新住所での開始手続き) |
全員 |
|
両手続きとも原則1週間前までに手続きが必要 解約手続きはインターネットもしくは電話で可能 開始手続きはインターネットや電話、郵送、FAXでも可能 |
| ガス (現住所の解約と 新住所での移転手続き) |
ガスを利用されている方 |
|
立ち会いが必要 繁忙期や年末年始はできるだけ早めに連絡する |
| 水道 (現住所の解約と 新住所での開始手続き) |
全員 | お客様番号 | 旧居の閉栓手続きを忘れると二重に支払う可能性がある 手続きは各地域水道部もしくは、インターネットや電話でも可能 |
| 固定電話の契約住所変更 | 固定電話を引いている方 |
|
引越し先の住所によって手続き内容や電話番号の取扱いが異なる 開通工事が必要になる場合があるため、早めに通信会社に連絡する |
| インターネットの移転 もしくは解約・契約の手続き |
全員 |
|
事前に新居の対応しているインターネットを確認しておく 個別にプロバイダとも契約している場合は、提供会社の引越し手続きが必要 |
| 火災保険・ 地震保険の住所変更 |
火災保険・地震保険加入者の方 |
|
引越し元・引越し先の居住形態により手続きが異なる |
| 国民健康保険の 資格喪失手続き |
他の市区町村に引越しする方で かつ会社員でない方 |
|
個人事業主が対象 手続きが遅れると保険診療が使えなくなる |
| 児童手当の住所変更 | 他の市区町村に引越しする方で かつ中学3年生までの子どもがおられる方 |
|
提出期限は転出予定日から15日以内 |
| 原付自転車の廃車手続き | 他の市区町村に引越しする方で かつバイク屋原付自転車を所有している方 |
|
バイクの種類によって手続き方法や必要な書類が異なる 他の市区町村に引越しする場合は、ナンバープレートの変更も必要 |
| 印鑑登録の廃止 | 他の市区町村へ引越しする人で かつ印鑑登録をしている方 |
|
旧住所で登録抹消の手続きをし、新住所で再登録の手続きを行う |
| 不用品や粗大ゴミの処分 | 全員 | – | 事前に処分方法を検討しておく |
引越し2週間前はライフラインの手続きや役所への手続きも増えてきます。
役所への手続きは1回でまとめて済ませられるよう、必要な書類を用意しておきましょう。
以下で、引越し2週間前にやることをそれぞれ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
12.季節ものなどの使う頻度が少ないものの荷造り
季節ものなどの使う頻度が少ないものから荷造りしていきましょう。
使用頻度の少ないものとは、以下のようなものがあります。
- クリスマスやひな祭りなどのイベントグッズ
- シーズンオフの衣類や靴
- 来客用の食器
- アルバムなど思い出の品
- 本やDVD
引越し 荷造りには基本的なコツがあり、ジャンル別に梱包の仕方が違います。
また、玄関から近い部屋から荷造りをしてしまうと生活に支障が出るため、荷造りは玄関から遠い部屋から始めましょう。
13.転出届の手続き
引越しをする前に旧住所の役所に「転出届」を提出しなければなりません。
では、転出届はいつから提出できるのでしょうか。
転出届は引越し日の14日前から当日までに提出しましょう。
期限内に提出できなければ罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
また、同じ市に引越しする場合は住民異動届、同じ区内に引越しする場合は転居届を提出しましょう。
14.電気|現住所の解約と新住所での開始手続き
引越しに伴う電気の手続きは、主に以下2つに分けられます。
- 現住所の電気解約手続き
- 新住所での電気開始手続き
電気の解約・開始はインターネットや電話での手続きが可能です。
手続きの際は、「お客様番号」「現住所」「名義人氏名」が必ず必要になります。
事前に準備しておくと、手続きがスムーズに行えるでしょう。
また、電力自由化によって新住所の電気は生活スタイルに合ったプランを選ぶことが可能です。
契約する電力会社によってプラン内容は異なります。
そのため、よく調べずに引越し手続きをしてしまうと、逆に電気代が高額になる可能性があるため注意しましょう。
15.ガス|現住所の解約と新住所での移転手続き
引越しに伴うガスの手続きも、主に以下2つに分けられます。
- 現住所のガス解約手続き
- 新住所でのガス移転手続き
ガスは他のライフラインとは違い、開栓作業に必ず立ち合いが必要になります。
そのため、繁忙期や年末年始はできるだけ早めに連絡をし、開栓作業の日程を抑えるようにしましょう。
また、ガスメーターが室内にある場合は、閉栓作業に立ち合いが必要になります。
一度閉めたガス栓は再度開栓ができないため、閉栓するタイミングに注意が必要です。
手続きは、インターネットもしくは電話でできます。
16.水道|現住所の解約と新住所での開始手続き
引越しに伴い現住所の水道の解約手続きが必要になります。
各水道局に電話もしくはインターネットから手続きが可能です。
もし、現住所の水道解約を忘れてしまうと、引越し後も旧居の水道代を支払わなければなりません。
引越しの1週間~2週間前までに申し込んでおくと良いでしょう。
新住所での水道開始手続きは、引越し後すぐ使えるように日時に注意が必要です。
17.固定電話の契約住所変更
固定電話の住所変更は、開通工事が必要になる場合もあるため、できるだけ早めにNTTへ連絡して工事予約を入れます。
引越し先の住所によって、手続きの方法や現状の電話番号が使えるかどうか異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
| 手続きの方法 | 電話番号の取り扱い | |
|---|---|---|
| 同一の市区町村に引越しする場合 | 移転手続きのみ | 現状の電話番号が使用可能 |
| 別の市区町村に引越しする場合(同都道府県内) | 移転手続きのみ | 現状の電話番号が使用不可 |
| 別の都道府県へ引越しする場合(同一エリア内) | 移転手続きのみ | 現状の電話番号が使用不可 |
| 別の都道府県へ引越しする場合(別のエリア) | 契約解除後、新住所にて再契約 | 現状の電話番号が使用不可 |
事前にどういった手続きが必要になるか、新旧住所がNTTのどちらの管轄になるか、確認しておきましょう。
同一市内以外の引越しは、現状の電話番号が使えなくなります。
また、NTT東日本とNTT西日本のエリアをまたいだ引越しの場合、固定電話 解約手続きが必要です。
固定電話を解約するとネット回線へ影響があるため、利用している電話回線を確認しておきましょう。
移転や解約のお問い合わせ先は以下の通りです。
| NTT東日本 | NTT西日本 | |
|---|---|---|
| 固定電話からの連絡先 | 116(局番なし) | 116(局番なし) |
| 携帯電話からの連絡先 | 0120-116-000 | 0800-2000116 |
| インターネットから | 電話のお引越し | お引越しのお手続き |
手続きの際は、以下のものを準備しておくとスムーズに手続きできます。
- 新旧の住所
- 電話番号
- 契約者氏名
- 電話料金の支払い状況がわかるもの
18.インターネットの移転もしくは解約・契約の手続き
引っ越しに伴うインターネットの手続きは、新居が対応しているインターネットを調べておく必要があります。
新旧居のネット回線が同じ場合は移転手続き、新旧所のネット回線が異なる場合は解約及び契約手続きを行わなければなりません。
また、個別にプロバイダーと契約している場合は注意が必要です。
インターネットを解約する場合は、プロバイダーによって解約締め日が異なります。
手続きが遅れると翌月分の料金を支払う可能性があるため、できるだけ早めに手続きするようにしましょう。
モデルやルーターといった機器をレンタルしている場合は、返却手続きも必要になります。
19.火災保険・地震保険の住所変更
火災保険の手続きは、新旧居の居住形態によって異なります。
手続きは、電話やインターネット、郵送でも可能です。
保険の異動や加入の場合は、保険会社によって手続き可能期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。
移動手続きの場合は、料金を再計算する必要があります。
また、保険を解約する場合は、引越し前の解約は避け、引越し後できるだけ早く手続きしましょう。
それでは、居住形態ごとに紹介していきます。
賃貸物件から賃貸物件に引越す場合
基本的に保険の異動手続きを行うだけで大丈夫です。
ただし、物件によっては管理会社が指定する保険会社に加入する必要があるため、事前に契約書などで確認しておきましょう。
賃貸物件から持ち家に引越す場合
現在の保険を解約し、新しく保険に加入する必要があります。
持ち家から賃貸物件に引越す場合
引越し先の物件を対象とした新しい保険に加入しましょう。
持ち家から持ち家に引越す場合
引越し元の持ち家をどうするかによって新しく保険に加入する必要があります。
引越し元の持ち家を売却する場合は、現在の保険の異動手続きを行いましょう。
また、地震保険は、火災保険に付帯して加入する保険のため、引越し後火災保険を継続する場合は地震保険も継続することができます。
火災保険を解約する場合は、地震保険のみ継続することはできません。
地震保険には割引制度があるため、利用する場合は「耐震性能評価書」や「耐震基準適合証明書」といった書類が必要です。
20.国民健康保険の資格喪失手続き
他の市区町村に引越しするため住民票を移動する方は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。
国民健康保険の手続きが遅れると保険診療が使えず、医療費が全額負担になります。
また、国民健康保険の再加入が遅れると、保険料をさかのぼって支払わなければなりません。
国保の資格喪失手続きが遅れると、口座引き落としのタイミングによっては、二重で保険料を払ってしまう可能性もあるため、気を付けましょう。
21.児童手当の住所変更
他の市区町村に引越しする方で、かつ中学3年生までの子どもがおられる方が必要な手続きです。
流れとしては、引越し元の役場での手続きと引越し先の役場での手続きの2つ必要になります。
引越し元の役場で児童手当受給事由消滅届を提出し、「所得課税証明書」を発行してもらいましょう。
所得課税証明書は、引越し先で児童手当を請求するのに必要な書類です。
引越してから15日以内に、引越し先の役場で「児童手当認定請求書」を提出します。
22.原付自転車の廃車手続き
他の市区町村に引越しする方で、原付自転車を所有している方が必要な手続きです。
引越し元の役場でナンバープレートを返却し、「廃車証明書」をもらいましょう。
ただし、原付自転車、軽二輪バイク、小型二輪バイクといったバイクの種類によって手続きや必要書類が異なるため、注意が必要です。
原付自転車(50~125cc)の引越しの場合
引越し先の役場で新しいナンバープレートを発行してもらいます。
その際に必要なものは、廃車証明書、標識交付証明書、新住所の住民票、印鑑です。
軽二輪バイク(126~250cc)の引越しの場合
引越し先の管轄陸運局で手続きをします。
必要なものは、車検証、自動車損害賠償責任保険証明書、新住所の住民票、印鑑、旧ナンバープレートです。
小型二輪バイク(251cc以上)の引越しの場合
引越し先の管轄陸運局で手続きをします。
必要な物は、手数料納付書、車検証、自動車損害賠償責任保険証明書、新住所の住民票、印鑑、旧ナンバープレートです。
申請書の用紙代やナンバープレート代と手数料がかかります。
23.印鑑登録の廃止
印鑑登録とは、住んでいる地域の役場に印鑑を登録することです。
あくまでも市内での登録印のため、他の市区町村に引越しする方は廃止手続きが必要になります。
基本的に、引越し元の役場で「登録抹消」手続きをし、引越し先の役場で「再登録」の手続きをしましょう。
手続き期限はありませんが、不動産取引や自動車登録などで必要になるため、早めに手続きしておくのがおすすめです。
申請時は、本人確認書類や登録している印鑑が必要になります。
24.不用品や粗大ゴミの処分
粗大ゴミとは、一辺が30cmを超えるものを指し、普段のゴミ出しでは処分できません。
引越し 不用品処分する方法は、以下のような方法があります。
- 引越し業者に不用品回収をセットで頼む
- 民間の不用品回収業者を利用する
- 自治体の粗大ゴミ回収を利用する
- リサイクルショップで売る
- フリマアプリで売る
- 友人・知人に譲る
それぞれメリットやデメリットがあるため、自分にあった方法を選びましょう。
引越し1週間前〜前日までにやることリスト|荷造りや手続きなど最終準備
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| よく使う日用品や冷蔵庫内の食材の処分 | 全員 |
|
よく使う日用品を梱包する場合は、フタは開けたままにしておく 冷蔵庫は空っぽにしておかないと運搬できないため、計画的に減らしていく |
| 郵便局の転送手続き | 全員 |
|
インターネットやポスト投函、郵便局窓口で手続き可能 転送の有効期限は届け出日から1年間 一度に同居する家族6人分まで届け出可能 |
| クレジットカードの住所変更 | クレジットカードをお持ちの方 |
|
更新後のカードを受け取るために必要 |
| 携帯電話の契約住所変更 | 携帯電話をお持ちの方 |
|
手続きは、電話やインターネット、店頭で可能 |
| NHKの契約住所変更 | 全員 | – | NHKのホームページから手続き可能 |
| 銀行口座の住所変更 | 全員 |
|
期限はないが、手続きが遅れると旧居に案内が届き個人情報漏洩の可能性がある |
| 各種定期配送の解約や配送先の住所変更 | ネット通販や定期配送を依頼している方 | – | 各通販サイトより手続き可能 |
| 衛星放送・ケーブルテレビの契約住所変更 | 衛生放送・ケーブルテレビを契約している方 |
|
アンテナやチューナーの取り外し・取付け工事が必要 |
| 新聞の契約住所変更 | 新聞購読をしている方 | 契約者情報 新旧居の住所 支払い方法 |
購読継続の有無に関わらず手続きが必要 配達をしてくれている販売店に連絡する |
| パソコンのデータのバックアップ | パソコンをお持ちの方 |
|
運搬中に破損する可能性があるため、バックアップが必要 荷物の紛失や破損には補償があるが、PC内データの内部故障は補償対象外 |
| 冷蔵庫の水抜き | 全員 | – | 引越し前日までに行う |
| 洗濯機の水抜き | 引越しをする方すべて | – | 引越し前日までに行う |
| 現住居のゴミ捨てと掃除 | 引越しする方すべて |
|
自治体のゴミ収集スケジュールを確認しておく ゴミが大量に出る場合は、事前に自治体に相談しておく 賃貸物件の場合は、原状回復できれば敷金が戻ってくる可能性がある |
| 新居のレイアウトを決める | 引越しする方すべて |
|
事前に決めておくと搬入がスムーズにできる ダンボールにどの部屋に運ぶか書いておく |
| 新居の下見と掃除 | 引越しする方すべて |
|
防カビ・防虫対策など合わせてしておく |
| 引越し業者からの引越し日の確認 | 引越しする方すべて | – | 基本的に引越しの2日前までに業者から連絡がある 日時や時間、荷物量など確認しておく |
| ダンボールの個数確認 | 引越しをする方すべて | – | ダンボールの紛失を防ぐために必要 ダンボールに番号を振っておき、管理リストを作っておく |
| 貴重品や高価なもの・手回り品などの準備 | 引越しをする方すべて |
|
現金や通帳といった貴重品は自分で運ぶ |
| 引越し費用の現金を準備 | 引越しをする方すべて |
|
当日現金で支払いの必要がある場合はおつりが出ないよう用意する |
引越し1週間前から前日までは、最終的な荷造りと身の回りの整理をしておきましょう。
とくに、気を付けたいのは冷蔵庫と洗濯機の処理です。
冷蔵庫は中身を空っぽにしておかないと、最悪運搬してもらえない可能性があります。
また、洗濯機も水抜き作業が必要です。
水抜きをしておかないと、運搬時に他の荷物が濡れてしまう場合があるため、必ず引越し前日までに済ましておきましょう。
以下で、引っ越し1週間前から前日までにやることを詳しく紹介していきます。
25.よく使う日用品や冷蔵庫内の食材の処分
1週間前からは、引越し当日まで使わないものやなくても問題ないものを梱包していきます。
引越し前日には、引越し当日に使うもの以外はすべて梱包しておくと良いでしょう。
新居ですぐ使うものや現金や通帳といった貴重品は自分で運べるようにまとめておきます。
また、引越し1週間前から冷蔵庫の中身を計画的に消費していきましょう。
引越し前日には空っぽにし、水抜き処理を済ませておくのが望ましいです。
26.郵便局の転送手続き
意外と忘れがちなのが、郵便局転送手続きです。
手続き方法は、インターネットやポスト投函、郵便局の窓口にて行えます。
転送手続きを忘れてしまうと、郵便物が差出人に戻ってしまい、重要な郵便物が受け取れません。
後々のトラブルにも繋がりかねないため、必ず転送手続きを行いましょう。
転送手続きは引越し日の1週間前から可能です。
ただし、転送届のデータが登録されるまで3~7営業日かかるため、手続きが遅いと旧居に郵便物が届いてしまうので注意しましょう。
転送手続きは、1度に6人家族まで可能です。
転送サービスの有効期限は1年間となっているものの、何度でも延長できます。
27.クレジットカードの住所変更
クレジットカードを利用している方が必要な手続きです。
利用明細書をwebで見ている方も、住所変更しておかないと更新後のカードを受け取ることができません。
更新後のカードは転送が認められてないため、住所変更をしないと受け取れないので注意しましょう。
手続き方法は、インターネットやコールセンター、郵送にて行えます。
28.携帯電話の契約住所変更
携帯電話の住所変更も必ず必要になる手続きです。
住所変更を行わないと請求書が旧居に届いて個人情報が漏洩したり、サービスの利用停止されたりと、様々なトラブルに繋がります。
手続き方法は、電話会社のホームページや電話、ショップの窓口で可能です。
手続き方法によって、必要なものが異なるため、注意しましょう。
| 必要なもの | |
|---|---|
| インターネットで変更する場合 | ログインユーザーIDとパスワード お客様サポートページに未登録の場合は、事前に登録が必要 |
| 電話で変更する場合 | 契約時に決めた暗証番号を入力する |
| ショップ窓口で変更する場合 | 新しい住所がわかる本人確認書類 利用中の携帯電話 |
29.NHKの契約住所変更
意外と忘れがちなのが、NHKの引越し手続きです。
手続き方法は公式ホームページから行えます。
書類の郵送の手間がないため、引越しで忙しくても手続きが可能です。
ただし、手続きが簡単だからといって後回しにしておくと、旧居で受信料が発生し続けてしまい、新居と合わせて二重請求される可能性もあります。
早めに手続きをしたい方は、引越し日の前月から手続き可能です。
30.銀行口座の住所変更
銀行口座も住所変更をしなければならない手続きの一つです。
手続き方法は、電話や郵送、銀行窓口があります。
インターネットバンキングを利用している方は、インターネットでの手続きも可能です。
| 必要なもの | |
|---|---|
| 電話で手続きする場合 | 口座情報や契約者住所、暗証番号など |
| 郵送で手続きする場合 | インターネットや窓口で申込書をもらう 必要事項を記入し、ポストに投函 |
| 窓口で手続きする場合 | 通帳と届出印が必要 |
31.各種定期配送の解約や配送先の住所変更
ネット通販での定期配送や牛乳などの配送サービスを利用している方は、解約もしくは住所変更の手続きが必要です。
手続き方法は、ネット上で行える場合がほとんどです。
しかし、中には電話や郵送での手続きが必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
32.衛星放送・ケーブルテレビの契約住所変更
衛星放送やケーブルテレビを利用している方が必要な手続きです。
引越し先でも利用される場合は、住所変更の手続きが必要になります。
アンテナやチューナーの取り外しや取付けも必要になる場合もあるため、早めの連絡を心掛けましょう。
33.新聞の契約住所変更
新聞を購読している方が必要な手続きになります。
引越し先でも継続して購読したい場合は、引越し先でも購読可能かどうか確認しておきましょう。
朝日新聞や読売新聞といった全国紙で引越し先にも販売店がある場合は、継続して購読が可能です。
手続き方法は、電話もしくはインターネットでできますが、販売店によって異なります。
34.パソコンのデータのバックアップ
パソコンのような精密機器をお持ちの方は、事前にデータのバックアップを取っておきましょう。
パソコンを業者に運搬してもらう場合、「運送業者貨物賠償責任保険」によって補償がありますが、あくまでもパソコン本体に対してのみです。
パソコンの内部データは保証の対象外となっており、いかなる場合もデータの補償はできません。
パソコンのデータバックアップ方法は機種によって異なります。
メーカーのサポートサイトをご覧いただくか、メーカーに直接お問い合わせください。
また、パソコンのデータ移動に関して、以下のアイテムを利用すると便利です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 外付けハードディスク | 移動できるデータ量が多い | 価格が高い |
| USBメモリ | データ移動がラク 価格が安い |
容量が少ない |
| オンラインストレージ | データ移動がラク | アップロードに時間がかかる |
35.冷蔵庫の水抜き
冷蔵庫の運び方にはコツがあり、注意しなければならないのは水抜きと霜取りです。
「水抜き」とは製氷機内の氷蒸発皿の水を捨てること、「霜取り」とは、冷蔵庫内に付いた霜を溶かすことを言います。
これら2つの作業はすぐにできるものではありません。
とくに霜取りは最低でも半日程度時間が必要になります。
引越し前日までには終わらせておくためにも、計画的に冷蔵庫内を空っぽにしましょう。
水抜き・霜取りの方法は以下の通りです。
- 事前に冷蔵庫の中身を空っぽにしておく
- タオルや新聞紙を用意し、製氷機能をオフにする
- 冷蔵庫の電源を切って、半日ほどドアを開けっぱなしにして氷を溶かす
- 蒸発皿を取り出して水を捨てる
- 冷蔵庫内のから拭きをする
また、冷蔵庫内を空っぽにしたら、掃除をしておくのがおすすめです。
普段は食品が入っているためなかなか掃除が出来ませんが、冷蔵庫内は意外と汚れています。
引越しを機に冷蔵庫の掃除を済ましておくと、新居でも気持ちよく使うことができますよ。
36.洗濯機の水抜き
洗濯機も冷蔵庫同様に、事前に水抜きを済ませておく必要があります。
洗濯機は内部に水が溜まっており、水抜きがしっかりできていないと運搬中に水が漏れたり故障の原因になったりするので注意しましょう。
洗濯機の水抜き方法は以下の通りです。
- 事前にタオルやバケツを用意し、洗濯槽を空っぽにしておく
- 水道栓を閉めてから電源を入れる
- フタを閉めて標準モードに設定し、スタートボタンを押す
- しばらく経ったら電源を切り、給水ホースを外す
※水が出てくる場合があるため、バケツなどをセットしておく - 電源を入れ、脱水ボタンを押す
- 脱水が終わったら、洗濯機内の水分をしっかり拭く
- 排水ホースを抜き、ホース内の水を抜く
37.現住居のゴミ捨てと掃除
現住居のゴミ捨てと掃除を行いましょう。
賃貸物件からの退去の場合、しっかり掃除をして入居当時の状態に戻すと敷金が戻ってくる可能性があります。
また、ゴミ捨てをする際は、自治体の収集スケジュールを確認しておきましょう。
ただし、指定された回収日でも、大量のゴミを出してしまうと収集車に積みきれず回収されない可能性があります。
大量のゴミを出す場合は、事前に自治体に連絡をしておきましょう。
38.新居のレイアウトを決める
荷造りをする際、あらかじめ新居のレイアウトと荷物の設置場所をイメージしておくのが重要です。
事前にレイアウトや収納場所を決めておけば、引越しがスムーズに進みます。
また、新居の各部屋とダンボールに番号を振っておきましょう。
どの部屋にどの荷物を運ぶのかわかりやすくなります。
さらに、それらをまとめた指示書を作成しておきましょう。
引越し当日、業者にもコピーして渡しておくと、効率的に荷物の搬入ができます。
また、過ごしやすい家具の配置方法は以下の2点です、
- 動線を意識して家具を配置する
- 目線をさえぎらないよう家具のサイズに注意する
動線を意識して家具を配置すると、部屋の中をスムーズに移動でき生活がしやすくなります。
食器棚や冷蔵庫の扉の開く向きや、クローゼットの扉の開き具合など、家具の配置を決める前にしっかり確認しておきましょう。
目線をさえぎらないような家具は、部屋を広く見せる効果があります。
部屋を広く見せたいのであれば、扉から奥へ行くほど家具が低くなるように配置しましょう。
コツを理解しても、部屋のレイアウトは難しいものです。
どうしてもレイアウトが出来ないという方は、家具配置のシミュレーションができるアプリを活用しましょう。
おすすめアプリは以下の通りです。
39.新居の下見と掃除
事前に新居の下見をしておきましょう。
下見の際に合わせてチェックしておく点は以下の通りです。
- キズや汚れはないか
- トイレの水はきちんと流れるか
- 窓やドアはガタついていないか
キズや汚れがあった場合は、必ず写真を取って残しておきましょう。
設備の不具合は、至急管理会社に連絡して引越し前に直してもらう必要があります。
カーテンや家具を購入する場合は、早めに計測した上で購入しておきましょう。
また、下見と合わせて掃除をしておくのもおすすめです。
新築の場合でも、ほこりが溜まっていたり汚れていたりする場合があります。
荷物が何も入っていないときに掃除をしておくと、隅々まで掃除ができますよ。
掃除と合わせて害虫対策や防カビ対策も行っておくと良いでしょう。
40.引越し業者からの引越し日の確認
ほとんどの引越し業者が、引越しの2日前までには連絡をしてきます。
引越し日時や荷物量など再度確認をしておきましょう。
前日までに連絡がない場合は、こちらから連絡しておくとトラブルを未然に防ぐことができます。
41.ダンボールの個数確認
荷物の紛失を防ぐためにも、ダンボールの個数チェックは欠かせません。
混載便などではとくに紛失しやすいため、必ずチェックしておきましょう。
番号などを振って、管理用リストを作っておくのもおすすめです。
42.貴重品や高価なもの・手回り品などの準備
現金や通帳、印鑑といった貴重品は自分で運ぶようにまとめておきましょう。
とくに貴重品は引越し当日も肌身離さず持っておく必要があります。
リュックサックやウエストポーチなどにまとめておくと、動きやすくて便利です。
43.引越し費用の現金を準備
引越し前日には、引越し用の現金を準備しておきましょう。
業者によっては、当日に現金のみ対応の場合もあるため、おつりが出ないよう準備しておくとスムーズです。
クレジットカード払いに対応している業者もあるので、見積もり時に確認しておきましょう。
引越し当日やることリスト|電気ガス水道立会いや住居の確認など
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 各家電の電源を切って配送する準備 | 全員 | 梱包資材 | ダンボールに入る小型家電の梱包 配線コードを外してまとめておく 洗濯機やテレビ、タンスといった大型家財は梱包しなくていい |
| 当日まで使うものを荷造り・梱包 | 全員 | 梱包資材 | タオルや歯ブラシといった当日まで使っていたものを梱包する |
| 電気・水道の停止と開始を確認 | 全員 | – | 旧居にてライフラインの停止、新居にて開始を確認する |
| ガス閉栓・開栓の立ち会い | 全員 | 新居で使うガス機器 | ガスメーターが屋内にある場合は閉栓にも立ち合いが必要 |
| 旧居に忘れ物がないか確認 | 全員 | – | 室外にあるものなどが忘れやすい |
| 引越しスタッフへ指示を出して荷物の運び出し | 全員 | – | 運び出す前に注意点や段取りの確認をする 気を付けて運んでほしい荷物は現物を見せる |
| 旧居の鍵の返却 | 賃貸物件に住んでいる方 | 旧居の鍵 | 返却方法は事前に確認する必要がある |
| 新居への移動 | 全員 | 貴重品 自分で運ぶ荷物 |
電気のブレーカーを下げる ガスの元栓と蛇口を閉める 戸締まりや忘れ物の確認 |
| 搬入荷物やダンボールの数の確認 | 全員 | – | 搬入した荷物やダンボールの数を引越し業者と一緒に確認する |
| 荷ほどきと荷物の整理 | 全員 | 荷ほどきの道具 | すぐに使うものから優先して荷ほどきをする |
引越し当日は、バタバタしていてとにかく忙しいものです。
旧居でやる作業と新居でやる作業などすべきことが多いため、余裕を持って行動できるよう工夫が必要になります。
前日に引越し当日の段取りを確認しておくようにしましょう。
引越し当日にやることを詳しく紹介します。
44.各家電の電源を切って配送する準備
電気ケトルや炊飯器といったダンボールに入る小型家電を梱包します。
基本的に、1つのダンボールに家電を1つずつ入れましょう。
梱包の仕方は以下の通りです。
- ダンボールの中央に家電を置く
- 家電の周りにふきんやラップといったキッチン内で使うものを詰める
- さらにタオルや新聞紙などで隙間を埋めて、家電を動かないようにする
テレビやレコーダーの配線も外してまとめておきましょう。
配線は外す前に写真を撮り、テープなどを貼り番号を振ったり、色付けしたりしておくと、新居で設置する際に分かりやすいです。
また、梱包の際に見失いやすいリモコンは、ひとまとめにして自分で運びましょう。
45.当日まで使うものを荷造り・梱包
タオルや歯ブラシといった当日まで使っていたものを梱包し、荷造りを完了させましょう。
引越し業者が来るまでに終わらせておくのが望ましいです。
万が一、業者が来るまでに終わっていなければ、追加料金が発生したり、引越しそのものがキャンセルされたりします。
後々のトラブルを防ぐためにも、業者が来るまでに終わらせておきましょう。
どうしても、当日までに荷造りが終わらない場合は、
- ひたすらダンボールに荷物を詰める
- 荷造りできなかった荷物は宅急便や自分で後から運ぶ
上記のような対応策があります。
荷ほどきの負担が増えたり、余分な費用が発生したりとデメリットもあるため注意が必要です。
45.電気・水道の停止と開始を確認
電気と水道の停止手続きは、立ち合いの必要はありません。
電気の停止はブレーカーを落としたら完了です。
引越し当日には、新居の電気や水道が使えるように段取りしておきましょう。
46.ガス閉栓・開栓の立ち会い
ガスの閉栓は、ガスメーターが屋内にある場合は立ち合いが必要になります。
ガスの開栓は必ず立ち合いが必要のため、余裕をもって新居に移動できるようスケジュールを組んでおくと良いでしょう。
また、やむを得ない場合は代理人でも立ち合いは可能です。
開栓作業の時間は15~20分程度が目安のため、わからないことがあれば作業中に質問することができます。
立ち合い当日までに、使用するガスコンロなども用意しておきましょう。
47.旧居に忘れ物がないか確認
引越し当日はバタバタして慌ただしくなりがちです。
そのため、忘れ物がないか入念にチェックしましょう。
意外と見落としがちなのが、
- ベランダの荷物
- 照明器具
- 洗濯機のホースやこまごまとした部品
- 自転車
- 押入れの天袋
- エアコンの室外機
などが挙げられます。
とくに、物干し竿は室外に置いていることもあり、ベランダの一部と化しているため忘れてしまう方が多いのでしょう。
室外や倉庫にあるものなど、しっかりとチェックしておく必要があります。
旧居の忘れ物は基本的に処分されてしまうため、万が一忘れ物をした場合はすぐに管理会社に連絡しましょう。
48.引越しスタッフへ指示を出して荷物の運び出し
荷物を運び出す前に注意点や段取りを確認しておきましょう。
とくに、気を付けて運んでほしい荷物は、現物を見せながら説明するのがおすすめです。
ダンボールには、新居のどの部屋に運ぶか記載しておくと運び出しがスムーズに進みます。
49.旧居の鍵の返却
賃貸物件に住んでいる方は、旧居の引っ越し作業終了後に鍵を返却しなければなりません。
一般的には、管理会社が旧居を訪問して大きな破損などないか確認してから返却をする場合がほとんどです。
しかし、管理会社によって鍵の返却方法が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
鍵を返却すれば、物件の明け渡しは完了となります。
50.新居への移動
荷物の搬出作業が終わったら、新居へ移動します。
移動前には以下のチェックをしましょう。
- 電気のブレーカーを下げる
- ガスの元栓と蛇口を閉める
- 戸締まりと忘れ物の確認
移動の前には、必ず業者と一緒に積み忘れた荷物がないか確認する必要があります。
新居での集合時間を決めておいて、業者よりも早く到着しましょう。
51.搬入荷物やダンボールの数の確認
荷物の搬入が終わったら、ダンボールの数に間違いがないか、破損しているものはないか確認しましょう。
確認作業は必ず引越し業者と一緒に行います。
52.荷ほどきと荷物の整理
荷ほどきや荷物の整理は、すぐ使うものから優先して行いましょう。
荷造りの際に「新居ですぐ使うもの」としてまとめた荷物を先に整理していきます。
また、荷ほどきを効率よく行うには、「ダンボールは部屋ごとに分けて運ぶ」ことが重要です。
そのためには、荷造りの段階でダンボールに運びこむ部屋を記載しておきましょう。
ただし、荷ほどきにはやってはいけないNG行動もあるため、注意が必要です。
- 手当たり次第にダンボールを開封する
- 複数のダンボールを同時に開封する
- 荷ほどきを後回しにする
手当たり次第にダンボールを開けたり、複数のダンボールを同時に開けたりすると、逆に効率が悪なってしまいます。
荷ほどきはタイムリミットがありません。
後回しにしてしまうと、何カ月も放置したままということもよくあります。
荷ほどきもあらかじめスケジュールを立てておき、リストアップしておきましょう。
引越し後にやることリスト|役所などで14日以内に終わらせるべき手続き
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 転入届もしくは転居届の提出 | 全員 |
|
転入届、転居届の手続きは引越し当日から14日以内に行なう 転入届の提出に合わせて住民票を取っておくと◎ 期限内に手続きができなければ、最大5万円の過料(罰金)がかかる |
| マイナンバーの住所変更 | 全員 |
|
引越し当日から14日以内に手続きをする |
| 国民年金の住所変更 | 国民年金の第1号被保険者に該当加入する方 |
|
手続きが遅れると正しい年金額を受給できなくなる |
| 運転免許証の住所変更 | 運転免許証をお持ちの方 |
|
住所変更をしないと罰金や科料に処される可能性がある |
| 車庫証明の住所変更 | 全員 |
|
車庫証明の住所変更をしないと罰金を科される可能性がある |
| 自動車・バイクの登録住所手続き | 自動車やバイクを所有している方 |
|
提出期限は原則引越し日から15日以内 |
| 児童手当の住所変更・転入手続き | 他の市区町村に引越しする方で かつ中学3年生までの子どもがおられる方 |
児童手当認定請求書 | 期限は引越し日から15日以内 |
| 犬の登録変更 | 犬を飼っている方 |
|
引越し後速やかに手続きが必要 登録変更を怠ると20万以下の罰金に処される可能性がある |
| 引越し先の学校の転校手続き | 学校に通う子どもがおられる方 |
|
– |
引越し後14日以内にやるべき手続きは多く、期限内にできなければ罰金が科されるものも多くあります。
引越し後 手続きは事前にしっかりと計画を立てて、段取りよく進めていきましょう。
53.転入届もしくは転居届の提出
引越し後には、新住所の役所に「転入届」を提出しなければなりません。
転入届も提出期限が設けられており、期限内に提出できないと罰則の対象になります。
では、転入届を引越し前に提出することはできるのでしょうか。
結論として、転入届は引越し前に提出することは、違反行為にあたります。
また、引越し先の住所によって、提出しなければいけない書類が異なるため、注意しましょう。
横にスクロールします
| 引越し先の住所 | 必要書類 | 手続き方法 | |
|---|---|---|---|
| 転入届 | 引越し元の住所から他の市区町村に引越した方 |
|
|
| 転居届 | 同じ市内に引越した方 |
|
|
引越し元の住所から同じ区内に引越した場合は、住民異動届の提出が必要です。
提出期限は、引越し当日から14日以内となっており、期限内に手続きができないと罰金がかかります。
54.マイナンバーの住所変更
引越しに伴い、マイナンバーカードの住所変更手続きもしなければなりません。
マイナンバーカードは、個々に個人番号が割り当てられたカードのことです。
全ての行政サービスをマイナンバーにて管理されているため、常に最新の情報が登録されていなければなりません。
マイナンバーの住所変更を怠ると、以下のようなリスクがあります。
- 最大で5万円の罰金が科せられる
- 転入届を提出から90日過ぎるとマイナンバーカード自体が失効
- 身分証明書として使えない
55.国民年金の住所変更
役場での国民年金の住所変更をしなければいけないのは「第1号被保険者」に該当する方のみです。
国民年金第3号被保険者に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きを行います。
転入届の手続きとまとめて行うと、効率的に済ませることができるので便利です。
手続きが遅れると以下のようなリスクがあります。
- 未納期間が発生し、年金受取額が減少する
- 正しい年金額が受給されない
56.運転免許証の住所変更
引越しに伴い、免許証の住所変更をしないとどうなるのでしょうか。
結論として、運転免許証の住所変更は、手続きを怠ると罰金や科料に処される可能性があります。
| 手続きできる場所 |
※いずれも新住所の場所 |
|---|---|
| 提出期限 | 明確な期限はなし なるべく「速やかに」 |
| 必要書類 |
|
| 代理人申請 | 都道府県により異なる 代理申請できる続柄が「同居家族のみ」と限られる場合が多い |
57.車庫証明の住所変更
自動車を所有している方は、車庫証明の住所変更も忘れてはいけません。
車庫証明とは、「車を保管する場所があります」というのを証明する書面のことです。
車庫証明の住所変更に必要な書類は以下の通りとなります。
| 駐車場が自己所有の場合 | 駐車場が他社所有の場合 | |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 〇 | 〇 |
| 保管場所標章交付申請書 | 〇 | 〇 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 〇 | – |
| 保管場所使用承諾証明書 (もしくは駐車場の賃貸契約書のコピー) |
– | 〇 |
| 自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの (住民票や運転免許証など) |
〇 | – |
| 収入証紙 | 〇 | 〇 |
| 印鑑 | 〇 | 〇 |
住所変更に必要な書類は、車庫として申請する駐車場の所有者によって異なるため、注意しましょう。
また、軽自動車は基本的に車庫証明の届け出が不要です。
ただし、自治体によっては必要な場合もあるため、事前に所管の警察署に確認しておきましょう。
手続き方法は、警察署に赴くかインターネット、代理人に依頼といった方法があります。
58.自動車・バイクの登録住所手続き
引越しに伴い自動車やバイクの登録住所を変更する必要があります。
管轄の陸運支局が変更になる場合は、ナンバープレートも変更しなければなりません。
必要書類が多く準備に時間がかかるため、しっかりを計画を立てて行いましょう。
| 手続きできる場所 |
※いずれも新住所の場所 |
|---|---|
| 提出期限 | 原則、引越し後15日以内 |
| 必要書類 |
|
| 手数料 | 登録手数料や申請書の用紙代 ナンバープレート代 ※地域によって異なる |
| 代理人申請 | 可 |
59.児童手当の住所変更・転入手続き
引越し元の住所から他の市区町村に引越しした方で、中学3年生までの子どもがおられる方が対象です。
新住所の管轄役所にて「児童手当認定請求書」を提出しなければなりません。
請求手続きには期限があり、引越し日から15日以内となっています。
15日を超えてしまうと、1カ月分の手当が受け取れない可能性があるため、早めの手続きを心掛けましょう。
60.犬の登録変更
ペットを飼われている方は、引越しに伴いペットの登録住所を変更しなければなりません。
この変更を怠ると、20万円以下の罰金に処される可能性があります。
| 手続きできる場所 |
|
|---|---|
| 提出期限 | 引越し後、できるだけ速やかに ※新しく飼育した日から30日以内 |
| 必要書類 |
|
| 手数料 | 登録料や注射済票交付手数料が必要 ※地域によって異なる |
| 代理人申請 | 不可 |
61.引越し先の学校の転校手続き
学校に通われている子どもがおられる方が必要な手続きです。
旧住所の役場でもらった「在学証明書」と「教科書図書給付証明証」が必要になります。
住民票の手続きの際に「転入学通知書」をもらっておき、まとめて転校する学校に提出しましょう。
引越し後にやることリスト|期日はないけど細々した早めに終わらせるべき手続き
横にスクロールします
| やること | 対象者 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 新居の近所への挨拶 | 全員 | 手土産 | 一般的に10時~17時頃が適切 近所への挨拶は引越し当日か引越し前が理想 |
| 荷ほどきと使用済ダンボールの処分 | 全員 | 荷ほどきの道具 | 荷ほどきは計画的に行う ダンボールの処分方法を事前に確認しておく |
| 勤務先への住所変更依頼 | 全員 | – | 勤務先のルールに従う |
| パスポートの住所変更 | パスポートをお持ちの方 | お持ちのパスポート | 住所のみ変更があった場合は特別な申請や届け出はない 氏名や本籍が変わった場合は手続きが必要 |
| サブスクや各種サービスの住所変更 | サブスクや各種サービスを利用している方 | – | 事前に手続き方法を確認しておく |
期限はありませんが、引越し後なるべく早く済ませておきましょう。
新居の近所への挨拶は早めに済ませておくと、今後の近似所づきあいがスムーズになります。
使用済みのダンボールも早めに処分して、新生活をより楽しいものにしましょう。
62.新居の近所への挨拶
マンションでは近所への挨拶をする文化が減少傾向にありますが、挨拶をしないことで悪い印象がついてしまう可能性があります。
できる限り近所への挨拶は行った方が良いでしょう。
とくに、マイホームなどの引越しの場合は、今後の近所づきあいや防犯のためにも挨拶は必要になります。
新居の近所への挨拶をするのに最適なタイミングは、
- 引越しの前日
- 日中(10時~17時ごろ)の時間帯
上記の日時がおすすめです。
引越し当日は、道路を塞いだり騒音を立てたりと迷惑をかけてしまうため、事前に挨拶を済ませておきましょう。
挨拶回りは日中に行なうのがベストです。
バタバタと忙しい午前中や、家族で団らんしている夜間に訪問するのは避けましょう。
また、引越しの挨拶で持参する手土産は、タオルやふきんといった消耗品をおすすめします。
手土産の相場は「500円〜1,500円」の間が主流です。
手土産は「気兼ねなく受け取れるもので、お返しが必要のない価格帯」のものを選びましょう。
63.荷ほどきと使用済ダンボールの処分
荷ほどきにタイムリミットはありませんが、計画を立ててできるだけ早めに終わらせましょう。
とくに、使用済みのダンボールはできるだけ早めに処分しないといけません。
理由としては、ダンボールは燃えるゴミとして処分することができないため、大量のダンボールを置いておくスペースが必要になるからです。
主な使用済みダンボールの処分方法は以下の通りです。
- 引越し業者に引き取ってもらう
- 回収業者に依頼する
- 自治体の指定する方法で処分する
- エコボックスを利用し、無料でダンボールを処分する
引越し業者の中には、「ダンボール引き取りサービス」を行っている業者もあります。
このサービスは大量のダンボールを一気に片づけることができるため、おすすめです。
ただし、ダンボール引き取りサービスは有料の場合が多く、繁忙期には回収できない場合もあります。
見積もり時に確認しておきましょう。
また、回収業者に依頼する場合は、業者によって無料になるか買い取りになるかわからないため注意が必要です。
中には、高額な費用を請求してくる業者もいるため、回収業者選びは慎重に行いましょう。
64.勤務先への住所変更依頼
会社勤めをされている方は、勤務先への住所変更依頼も必要です。
手続きは、勤務先のルールに従って行いましょう。
変更申請を怠ると、会社から支給される通勤手当に差が出てしまいます。
年末調整などの書類などが手元に届かないというトラブルにもなりかねないため、できるだけ早めに変更申請を行いましょう。
65.パスポートの住所変更
引越しに伴い住所のみが変更になった場合、特別な申請や届け出は必要ありません。
パスポートの住所変更の流れは以下の通りです。
- パスポートの裏表紙中面の「所持人記入欄」を確認する
- 旧住所を記入している場合は、上から二重線で消す
- 欄内に新住所を記入する
ただし、パスポートに記載されている本籍の住所が都道府県をまたいで変更になった場合は、記載事項変更手続きを行う必要があります。
| 届出場所 | 各都道府県の旅券センター窓口 |
|---|---|
| 提出期限 | なし |
| 必要書類 |
|
| 手数料 | 新しく作り直す場合は、6,000~1万6,000円 記載事項変更手続きの場合は、一律6,000円 |
66.サブスクや各種サービスの住所変更
サブスクや各種会員サービスの住所変更も忘れずに行いましょう。
手続き方法は、電話やインターネット、店頭での手続きが可能です。
住所変更が完了していないと、重要な連絡が届かない場合があります。
また、振込用紙で支払いになっている場合は、新しい住所に支払い用紙が届かない可能性も。
複数のサブスクなどのサービスを利用している方は、漏れがないかしっかりと確認してくださいね。
引越し準備でやることに関するよくある質問
ここから、引越し準備でやることについて以下3つのよくある質問を紹介します。
- 引越し準備はいつから始めるべき?
- 一人暮らしの引越しスケジュールは?
- 引越し準備が進まない時の対処法は?
- 引越しするときに一番最初にやることは何ですか?
- 引越しで一番大変なことは何ですか?
ぜひ参考にしていただき、疑問解決に役立ててください。
引越し準備はいつから始めるべき?
引越しは一人暮らしか家族での引越しかによって、準備を始めるタイミングが異なります。
一人暮らしの場合は、家族での引越しと比べ荷物量ややるべき手続きが少ないため、おおよそ1カ月前から始めておけば問題ないでしょう。
家族での引越しで、子どもがいる場合は学校関連の手続きも増えてきます。
家族での引越しは1.5〜2か月前から始めておくと慌てずに進められるでしょう。
一人暮らしの引越しスケジュールは?
一人暮らしの引越しでも、事前にしっかりスケジュールを立て、やるべきことをリスト化しましょう。
一人暮らしだからといって、引越しのスケジュールは変わりません。
さらに、一人暮らしの場合は、全ての手続きを一人で行わなければならないため、より計画的に動く必要があります。
役所の手続きをまとめて行ったり、荷物量を少なくしたりするとスムーズに準備を進められるでしょう。
引越し準備が進まない時の対処法は?
仕事や育児で忙しく、引越し準備が進まない方も多いでしょう。
ただし、荷造りは引越しをする方の義務とされています。
そのため、引越し当日までに荷造りができていないと、最悪の場合引越しそのものをキャンセルされる場合もあるのです。
1 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
参照:標準引越運送約款
しかし、荷物量が少ない場合や追加料金を支払えば、引越し業者が荷造りを手伝ってくれる可能性もあります。
引越し準備は最初にしっかりと計画を立てることが重要です。
また、やるべきことをリスト化し、さらに見える化することで効率的に準備を進められます。
しかし、引越しはやるべきことが多く、荷造りや荷ほどきを自分でやる時間がない場合は、引越し業者の「荷造り・梱包サービス」を活用しましょう。
荷造り・梱包サービスとは、荷造りから対応してくれる引越し業者のサービスの一つです。
中でも、サカイ引越センターの「荷造りお任せパック」をおすすめします。
荷造りお任せパックとは、荷造りから荷ほどき、新居の掃除まで専門スタッフが行ってくれるサービスです。
忙しく荷造りだけでもプロに頼みたいという方は、ぜひ利用してみてください。
引越しするときに一番最初にやることは何ですか?
引越しするときに一番最初にやることは、まず引越し日時や業者を決めること。
また、報告が必要な先へ引越しするという事前連絡です。
引越し先が決まったら準備することでも紹介した以下のリストを参考にみてみましょう。
- 1.引越し先の情報を確認
- 2.現住居の退去を管理会社に連絡
- 3.現住居の駐車場の解約を管理会社に連絡
- 4.引越し日を決める
- 5.引越しの見積もりを複数社取る
- 6.引越し業者を決定して依頼
- 7.ダンボールなど梱包資材の受け取り
- 8.退去手続きの書類を提出
- 9.学校の転校手続き
- 10.幼稚園・保育園の転園届の提出
- 11.介護保険被保険者証の手続き
トラブルが発生したり、手続きがスムーズにできなかったりすることを考えて、どれも早めの連絡がおすすめです。
また、現住所の契約解除の連絡など、忘れてしまうと大きなトラブルになりかねません。
ぜひリストを参考に、自分が連絡・手続きしなければならない項目をチェックしてみてください。
引越しで一番大変なことは何ですか?
引越しで一番大変なことは、代行できない自分でしかできない手続きではないでしょうか。
荷造りや運搬も体力的に大変ですが、予算を上げれば引越し業者に依頼して負担を減らすことも可能です。
引越しでは必要な手続きが多く、以下のような事項は自分で手続きする必要があります。
- 現住居の退去連絡や手続き
- 学校の手続きや連絡
- 役所での転出転入などの手続き
- 電気やガスなどの手続き
- さまざまな契約の住所変更
引越し前に手続きが可能な項目は、早めにまとめて済ませておくことがおすすめです。
まずは、必要な手続きや連絡をリスト化することからはじめましょう。
できるだけ引越しを楽に済ませたいなら、引越しで代行できる部分を業者に依頼してみてはいかがでしょうか。
まとめ|引越しやることは準備が大事!チェックリストを活用して計画的にやろう
引越しはやることが多く、漏れがないようにするためにはチェックリストの活用がおすすめです。
大まかなやることを覚えていても、細かな手続きや連絡を忘れがち。
ぜひこの記事で解説した、引越し1ヶ月前から当日までにやることリストを参考にしてください。
また、以下の引越し準備リストも一緒に活用してくださいね。
解説したように引越しはやることが多いので大変です。
そんな引越しを少しでも楽に済ませるなら、荷造りなどを依頼できる引越し業者の利用がおすすめ。
サカイ引越センターは、スタッフに依頼できる部分をプランによって選択ができます。
「荷ほどきは自分で」「荷造りから荷ほどきまで」など、自分にあったプランが選べますよ。
引越しの荷造りを依頼したい方は、ぜひサカイ引越センターを利用してみてください。
サカイ引越センター以外の引越業者も比較して決めたい!
希望の条件を入力するだけで、まとめて複数の業者に引越しの見積もりを依頼できます。
なかでも、口コミ数の多い「引越し侍」が参考になるのでおすすめです。
引越しの見積もりサイトを利用したい方は、ぜひ以下の表を活用して選んでください。
横にスクロールします
| 見積もりサイト | 
引越し侍 |

くらしのマーケット |

DOOR引越し見積もり |

引越しラクっとNAVI |
|---|---|---|---|---|
| おすすめな人 | 大手引越し業者も含めて料金比較をしたい人 |
別の引越し作業も合わせて依頼したい人 |
赤帽の料金も含めて比較したい人 |
業者とのやり取りを代行してほしい人 |
| 提携業者数 | 340社〜 | 590社〜 | 130社〜 | 60社〜 |
| 依頼業者の選択 | 可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
| 電話番号入力 | 必須 |
必須 |
必須 |
必須 |
| 口コミ件数 | 80,000件〜 | 非公開 | 16件 | 50件〜 |
| 公式サイト | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |


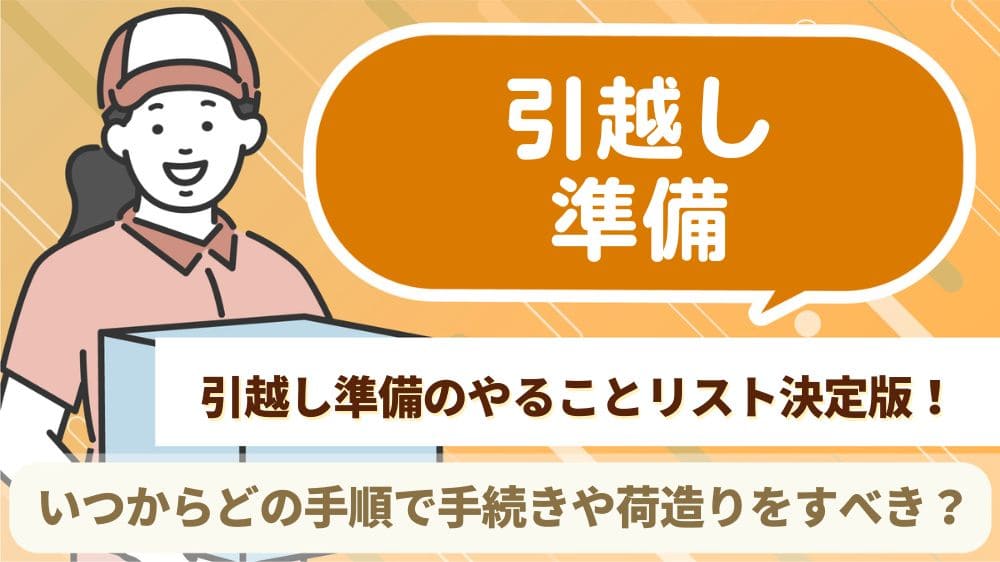


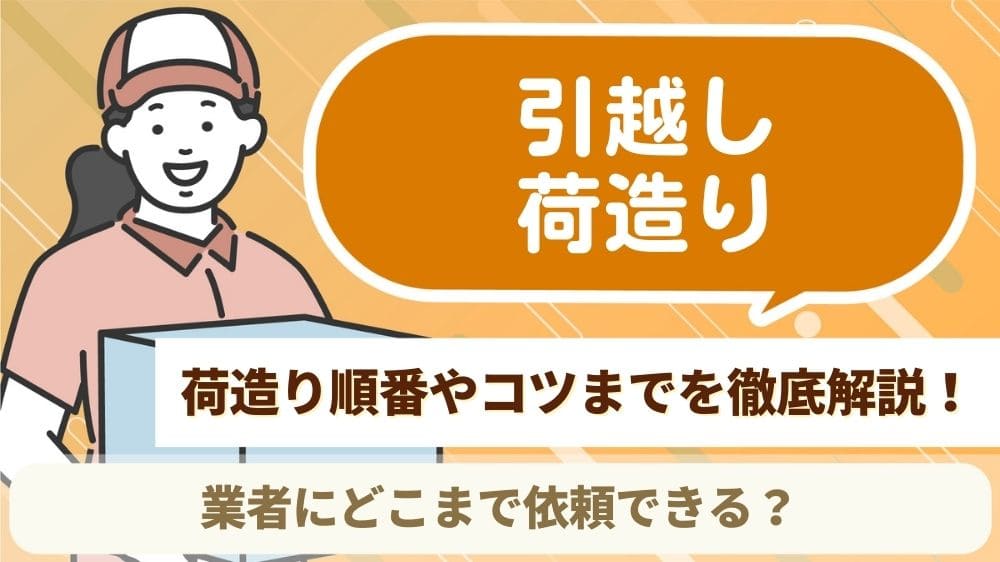
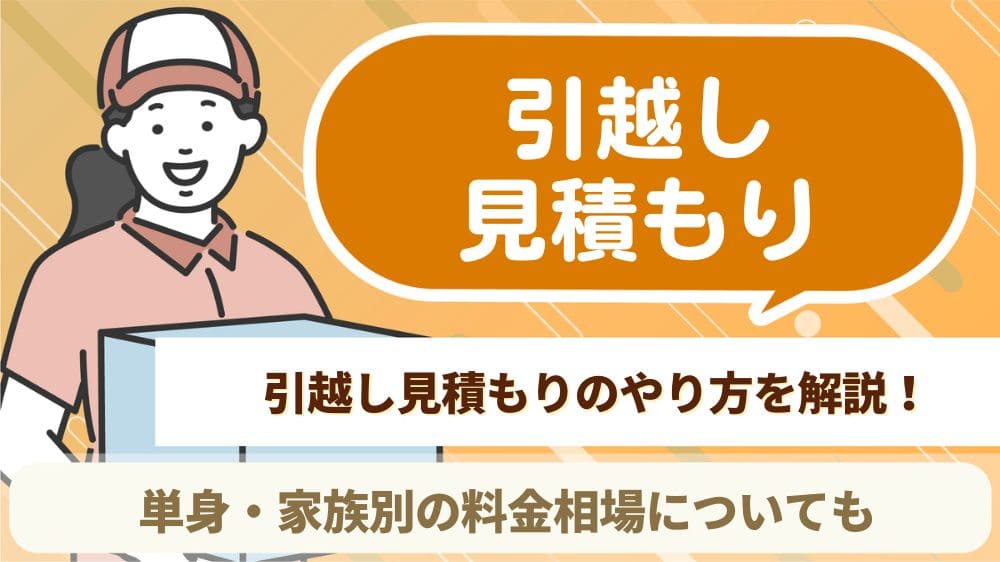
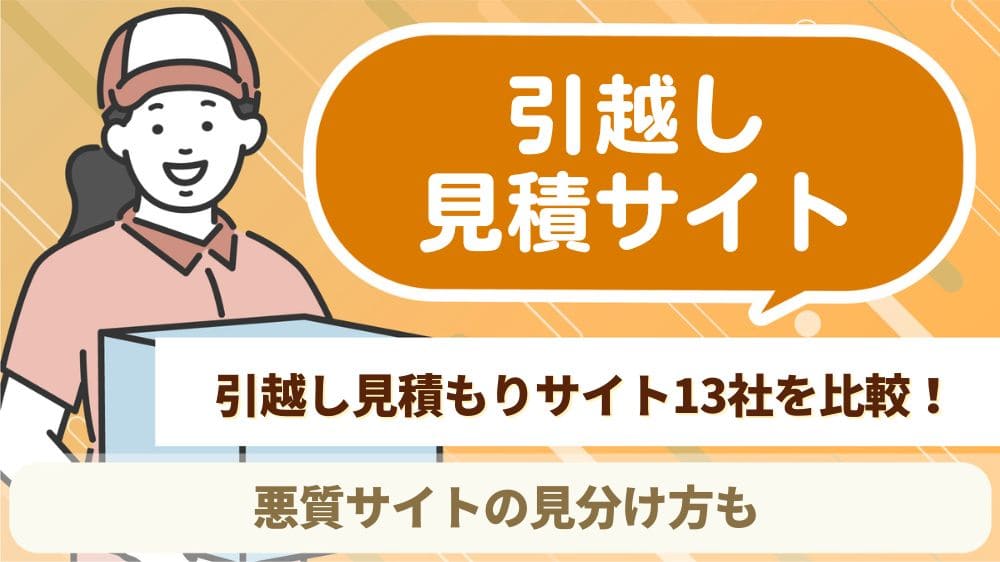
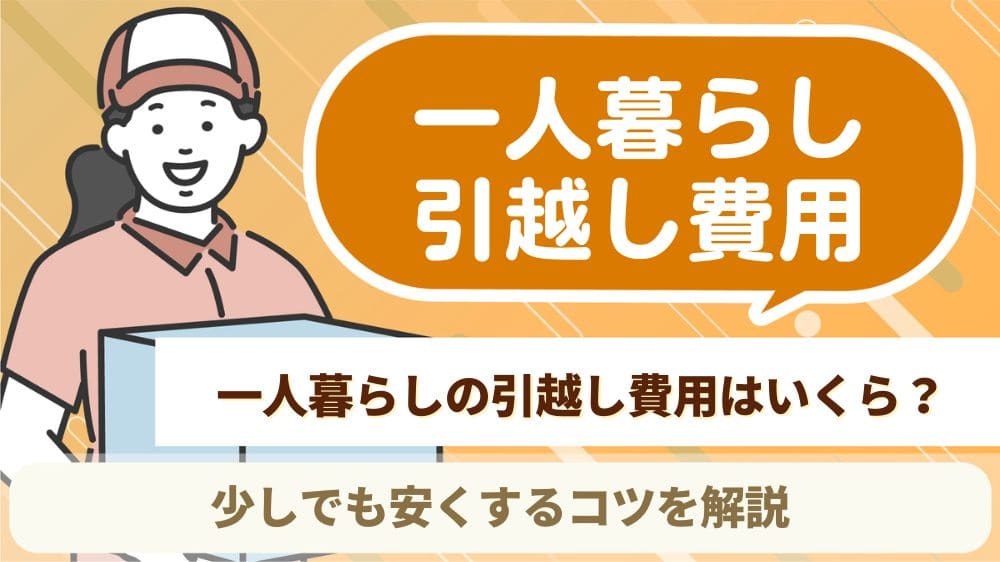
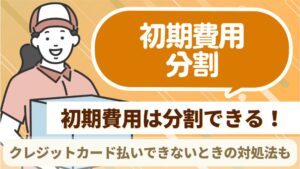
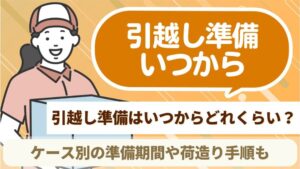
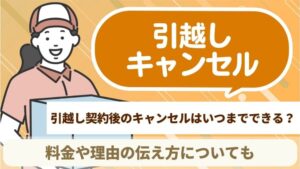
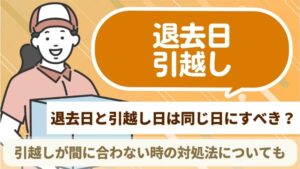
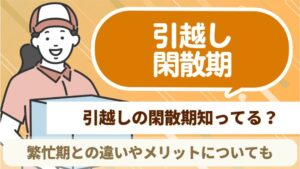
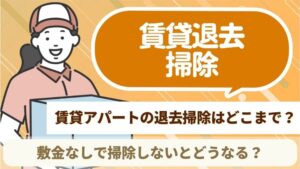
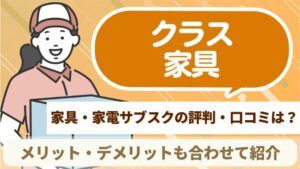
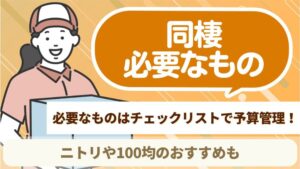
そんな方には、料金やサービスを比較できる見積もりサイトがおすすめです。