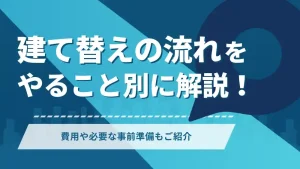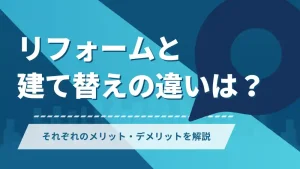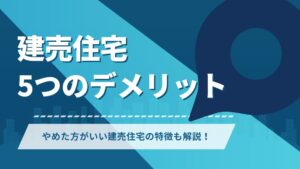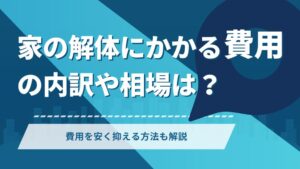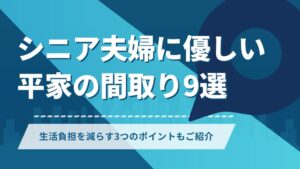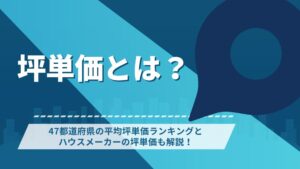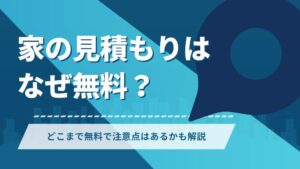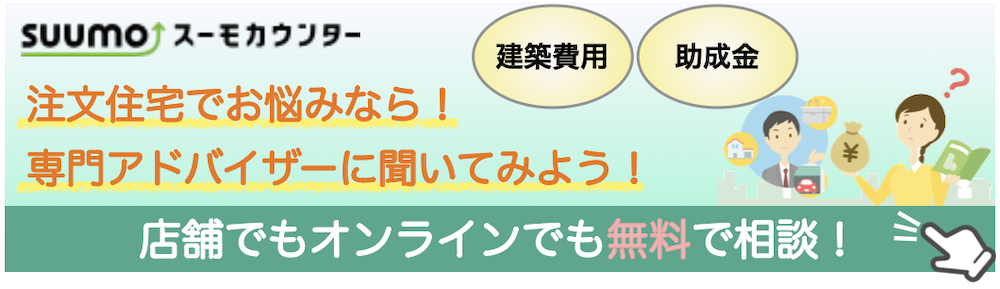
狭い土地の活用方法!土地の売却方法や気を付けたい法規制も解説
本ページはプロモーションが含まれています

相続などにより土地を手にする機会がありますが、全ての土地が使い勝手の良いものとは限りません。
立地はもちろん、土地の形も使う側にとって大きな影響をもたらします。
そこでこちらのページでは、もし狭い土地を手にした場合、どのような活用方法があるのか紹介します。
狭い土地でも住宅が建てられるのかや、狭い土地ならではのメリット・デメリットについてもお話ししますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
目次
狭小地とは
狭小地とは、文字通り狭い土地を意味する言葉です。
しかし、具体的にどれくらい狭ければ狭小地とは決まっていません。
一般的には15~20坪以下の土地を意味すると言われています。
また、狭小地には三角形や台形のような不整形地が多く、活用方法が限られることが多いです。
そして、狭小地の上に建てられた物件のことを、狭小住宅と呼びます。
狭小住宅は住みづらいイメージを抱く方もいるかもしれませんが、土地購入費はもちろん住宅建設後に発生する固定資産税を安く抑えることができます。
そのため、あえて狭小住宅を選ぶ人もいるほどです。
狭小地の特徴
狭小地の特徴として以下のようなものが挙げられます。
- 15〜20坪以下
- 三角地や台形地のような不整形地が多い
- 都市部など坪単価の高い住宅密集地にある
狭小地は土地の面積は狭いものの、坪単価の高い住宅密集地にあることが多く、利便性が高いのが魅力です。
面積が小さい分、土地の購入にかかる費用も抑えられるため、なるべくコストをかけずに、都市部の便利な場所に住みたい方におすすめです。
狭小土地の住宅間取り
狭小土地を活用して住宅を建設する場合、居住面積を広く取るため3階建てにしたり、地下を作るのが一般的です。
その他にも、光を取り込みやすくするために吹き抜けや天窓を設けるなどといった間取りを組むこともあります。
フロアごとに生活導線をしっかりと意識して作り込めば、コンパクトで非常に住みやすい住宅にすることができます。
狭小地に住宅建築を行う際には、間取りにこだわる必要があるため、建築費用は高くなる傾向にあります。
しかし、土地や住宅の面積などにより決定される固定資産税が安く抑えられたり、居住空間が狭いので冷暖房費が抑えられる可能性があります。
建築費はかかるかもしれませんが、その分入居後の支払いが少なく済むのは魅力的ですね。
狭い土地の活用方法
それでは狭小地を手にした場合、どのように活用することができるのでしょうか。
今回は、狭い土地の活用方法を6つご紹介します。
それぞれの活用方法における初期費用と収益性、メリット・デメリットを一覧表で比較してみましょう。
| 活用方法 | 初期費用 | 収益性 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 駐輪場経営 | ◯ | ◯ | ・収益化しやすい ・すぐに運用できる |
・放置自転車などに 悩まされる可能性がある |
| 土地の貸し出し | ◎ | ◯ | ・すぐに運用できる | ・安定した収益が見込めない |
| 建物の貸し出し | △ | ◎ | ・収益率が高い ・節税効果が期待できる |
・初期費用がかかる ・長期的な運用が求められる |
| 自動販売機の設置 | ◎ | △ | ・手軽に始められる | ・収益率が低い |
| コインランドリー経営 | ◯ | △ | ・ニーズが高まっている ・物件を貸すより運営しやすい |
・初期費用がかかる ・長期的運用のためリピーターを つける経営計画が必要 |
| コインロッカーの設置 | ◯ | △ | ・自動販売機と比べて 収益率が高い |
・立地によっては 需要が無い |
駐車場や駐輪場を経営する
狭小地は、駐車場や駐輪場として運営することが可能です。
コインパーキングとして運営する場合、精算機など機械を設置する必要があります。
そのため、10坪の土地で2台ほど駐車ができます。
コインパーキングではなく月極の駐車場とした場合には、もう少し駐車台数を増やせます。
狭小地は都市部の人口密集地に多く存在します。
駅が近い利便性の優れたエリアにある土地ならば、ある程度の需要も見込めるためおすすめです。
月極駐車場であれば、白線を引くだけですぐに運用ができる手軽さも、駐車場運営の魅力です。
もし土地が10坪を下回るような場合には、駐輪場にしてしまうのも一つの手です。
ロック板設置など設備を整える必要がありますが、こちらも比較的すぐに運用が可能です。
スペース次第では、荷物を保管しておけるコインロッカーなどと併用して収益を得るのもおすすめです。
ただし放置自転車や違法駐車のようなトラブルに見舞われるリスクもあります。
トラブル対応に不安を感じる方は、運営や管理をしてくれる会社に委託するのも一つの手です。
土地を貸し出す
なるべく初期費用を抑えて活用したい方には、土地を貸し出す方法がおすすめです。
収益性はあまり大きくはありませんが、手軽かつローコストで始められるのがメリットです。
ある程度人通りのある場所であれば、ランチ販売や青空ギャラリーとして貸し出すことができます。
月極などで貸し出せば、ある程度安定した収益が見込めます。
そのため、使っていない日がないように、上手くスケジュール管理を行っていく必要があります。
もし、ランチ販売や青空ギャラリーとしての収益が見込めない場合には、車中泊スポットとして活用するのもおすすめです。
アウトドア人気が高まる中で、車中泊ができる場所はまだまだ少ないのが実情です。
車中泊スポットであれば、比較的どのような立地でも、ある程度の需要が見込めます。
土地の貸し出しは、比較的準備も不要で手軽に行えるのが魅力ですが、電気や水道といった設備があると、より活用の幅が広がります。
建物を建てて貸す
土地の運用として最も一般的な方法が、アパートやマンションを建設し、人に貸すというものです。
他の方法と比べると、どうしても初期費用がかかってしまうものの、収益性は圧倒的に優れています。
先ほどもお話ししたように、狭小地は都市部の人口密集地に多いです。
持っている土地が駅の近くであれば、ある程度の需要が期待できます。
駅徒歩圏内であれば、利用者は車を持つ必要が無いため、駐車場を備えていなくても問題ありません。
しかし、全ての狭小地が利便性の高い駅近くにあるわけではありません。
建物を建てて貸す場合には、その立地場所によって建物を選ぶようにしましょう。
例えば、持っている土地が閑静な住宅地にある場合には戸建てに、人の行き交う場所にある場合にはコンビニや飲食店といった具合に検討してみると良いでしょう。
自動販売機を設置する
どれほど狭い土地でも活用できる方法として、自動販売機の設置が挙げられます。
それほど大きな場所を取らずに設置できる自動販売機は、ある程度の人通りがある場所であれば収益が見込めます。
しかし、あまり収益率は良いとは言えないので、コインパーキングなど他の活用方法と組み合わせてみられることをおすすめします。
また、自動販売機を設置した場合、商品の補充など定期的な手入れも必要なので、業者への委託も視野に入れて検討してみましょう。
コインランドリーを経営する
夫婦共働きの家庭や単身世帯の増加により、需要が高まっているのがコインランドリーです。
アパートやマンションなどが多い場所にあれば、十分に収益が見込めます。
また、基本的に無人で運営できるため、経費がかからない点も魅力です。
コインランドリーを利用する際には、待ち時間が発生するため、自動販売機の設置を合わせて行うのもおすすめです。
しかし、洗濯機や乾燥機などといった設備を揃える必要があるため、初期費用がかかる点には注意が必要です。
コインロッカーを設置する
狭小地が、繁華街や観光地近くにある場合には、コインロッカーを設置する方法もあります。
邪魔になる手荷物を預けて、自由に観光を楽しみたいという方が多ければ、収益が見込めます。
立地によっては自動販売機を設置するより儲けが出る可能性もあります。
ただし、コインロッカーの設置については、立地条件が非常に重要となるため、十分に検討したうえで活用してくださいね。
活用方法に迷ったらHOME4Uに相談する
ここまで狭い土地の活用方法をいくつか紹介してきました。
すぐに運用できそうなものから、準備が必要なものまで、色々な使い方ができそうですね。
しかし、どの活用方法もメリットとデメリットが存在します。
立地条件によっては、あまり収益が期待できない活用方法もあります。
あなたが今持っている狭小地は、どの方法なら大きな収益を生み出せそうですか?
正直よく分からないという方は、プロに相談してみるのがおすすめです。
HOME4Uでは、アパート経営・マンション経営・駐車場経営などの土地活用・不動産投資について、複数の企業から同時に一括でプラン請求ができるサービスです。
全国各地の大手企業と連携しており、活用したい土地の情報を入力するだけで、一度に最大10社までプラン請求が行えます。
そのため、一社ごとに連絡を取り、土地の状況や要望を説明する必要がないのです。
圧倒的な時短にもなりますし、負担軽減にも繋がりますよね。
さらに、一度に複数社のプランをチェックできるので、収益最大化に向けて比較しやすいのもHOME4Uの魅力です。
高いセキュリティ技術と事業規模を誇るNTTデータグループが運営しているので安心して利用できます。
最大10社までプランを請求できるので、なるべく多くの会社の収益最大化プランを比較して、今持っている土地を最大限活用できる方法を探ってみましょう!
無料で最大10社に収益化最大プランを請求!
狭い土地を購入・所有するメリット
何か事業を始めるにあたって、狭い土地を購入するのも一つの手です。
わざわざ狭い土地を購入する必要はないようにも思えますが、実は以下のような狭い土地を購入・所有するメリットもあるんです!
- 土地の購入費が安い
- 資産になる
- 固定資産税が安い
土地の購入費が安い
まず第一に土地の購入費が安いことです。
狭小地は一般的に10〜15坪ほどの土地を言います。
都市部など人口密集地にあることの多い狭小地ですが、同じ坪単価であっても土地が小さければ、購入費用もある程度抑えられます。
また、土地の形や大きさ次第では、なかなか買い手が付かず、相場よりも坪単価が低めに設定されていることもあります。
事業を始める際にも整備する土地面積が小さい分、初期費用を抑えることができますね。
資産になる
狭い土地でも、活用方法次第では収益を得ることもできます。
住宅にするのが難しい大きさでも、駐車場やコインランドリーなど、先ほど紹介したような事業に活用できます。
そのエリアの環境やニーズを理解できれば、しっかりと収益化できることでしょう。
活用方法に悩んだときには、HOME4Uのようなサービスを使って、プロに相談するのもおすすめです。
固定資産税が安い
建物や土地に毎年かかってくるのが、固定資産税です。
固定資産税は、土地の広さに比例して高くなります。
狭い土地では、土地の面積が小さい分、必然的に固定資産税も安くなります。
初期費用だけでなく、ランニングコストも安く抑えられるのが嬉しいですよね。
狭い土地を購入・所有するデメリット
様々なメリットを持つ狭い土地ですが、当然デメリットも存在します。
デメリットには以下の2つがありますので、それぞれ確認していきましょう。
- 狭い土地は売れない・売れにくい
- 住宅のデザインが制限される
狭い土地は売れない・売れにくい
狭い土地は、立地条件によっては使い道が限られてしまうため、買い手が付きづらい場合があります。
購入にかかる費用が抑えられるのがメリットである一方、反対に自分が売りたいと思った時にもある程度価格を落とす必要が出てきてしまうことも……
住宅のデザインが制限される
狭い土地を住宅にする場合には、デザインが制限される可能性があります。
ただ、土地が狭いために希望の設備を同じフロアに設けられないだけでなく、「建築基準法」により制限される部分があるためです。
土地の場所や面する道路幅などによっては、隣の土地への日当たりや風通しのため、高さが制限される場合も。
狭小住宅3階建てで建てられることが多いため、デザインが制限されるかもしれません。
希望の条件を満たした住宅の建築が可能かどうか、事前にチェックしておく必要があります。
狭い土地を活用する際に気を付けたい法規制
先ほど「建築基準法」について少しお話ししましたが、土地活用には法律も絡んできます。
あなたが持っている土地ですが、好き勝手に使える訳ではありません。
特に狭い土地を活用する際に気を付けたいのが、以下の4つです。
- 用途地域
- 建ぺい率や容積率
- 接道義務
- 防火規則
それぞれどのような規制なのか、詳しく紹介していきますね。
用途地域
用途地域とは、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進を目的として、行政により定められた土地の用途の分類です。
住居専用地域や、商業地域、工業地域など全部で13種類に分類されます。
エリアごとに建てられる建物の高さや店舗の広さが決められています。
そのうち、住居建設に大きく関わってくるのは8種類です。
それぞれのエリアごとに建てられる建物の特徴について、簡単にご紹介します。
| 用途地域 | 建物の高さ | 建物の種類 | 店舗建築 |
|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 10メートル または 12メートル以下 |
住居・交番・小中学校・老人ホームなど | 床面積150㎡以下 |
| 第2種低層住居専用地域 | 10メートル または 12メートル以下 |
住居・コンビニ・飲食店など | 床面積150㎡まで |
| 第1種中高層住居専用地域 | ー | マンション・教育施設・図書館・病院など | 2階建て以内&床面積が500㎡以下 |
| 第2種中高層住居専用地域 | ー | スーパー・商業施設・飲食店など | 2階建て以内&床面積1500㎡以下 |
| 第1種住居地域 | ー | 住宅・商業施設・事務所・ホテルなど | 床面積3000㎡まで |
| 第2種住居地域 | ー | 住宅・大型商業施設・ボーリング場・カラオケ店など | パチンコ・カラオケボックスの場合、 床面積10000㎡以下 |
| 準住居地域 | ー | 劇場・映画館、営業用倉庫・自動車修理工場など | 床面積が150㎡以下の自動車修理工場、 客席部分200㎡未満の劇場や映画館 |
| 田園住居地域 | 10メートル または 12メートル以下 |
住宅・教育施設や図書館、病院・農家レストランなど | 農産物直売所や農家レストランの場合、 床面積が500㎡以下 |
このように用途地域によって、建設できる店舗の大きさや住居の高さが制限されます。
狭い土地に住宅を建てる際には、3階建てにして床面積を増やす必要があるため、特に高さ制限は注意しておきたいポイントとなります。
建ぺい率や容積率
建ぺい率とは、土地に対して建てられる建物の建築面積の割合のことを言います。
つまり建ぺい率が高いほど、土地いっぱいに建物を建てることが可能です。
なお、建ぺい率は、建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100で計算します。
また、建物の建築面積だけでなく、全てのフロアの床面積を合わせた延床面積についても、土地の大きさに対する割合が決められています。
これを容積率と呼び、容積率(%)=延べ床面積/敷地面積×100で計算します。
建ぺい率も容積率も、用途地域によって上限が決まっています。
制限値を超える構造の住宅は違法建築とみなされ、審査が通りません。
| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第2種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第1種住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第2種住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 準住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 田園住居地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
接道義務
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定で、都市計画区域内で建物を建てる場合に守らなければならない決まりです。
道路から自由に出入りできるといった目的の他、消防活動の妨げになるのを防ぐためにも必要な制度です。
接道義務によって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられません。
奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上なければなりません。
防火規制
防火規制とは、火災による危険から市街地を守るために設けられた制度です。
建物の密集度が高い駅前などのエリアや幹線道路沿いなどを防火地域・準防火地域と指定し、建物の階数や延べ面積に応じて、建物の資材や構造を規制しています。
建物が密集しているエリアでは火が燃え広がるのを防ぐことを目的として、幹線道路沿いでは消防活動の妨げにならないことを目的として指定されます。
防火地域に該当する場所に3階以上の建物を建てる場合、鉄筋コンクリート造や耐火被膜した鉄骨造などの耐火構造になっている必要があります。
準防火地域でも、耐火被膜した木造住宅など一定の基準を満たした設計にする必要があります。
防火地域については、各市町村ごとに情報を公開しています。
”調べたい市区町村名 防火地域”で検索してみてくださいね。
狭い土地の活用に関するよくある質問
最後に、狭い土地の活用に関するよくある質問を3つご紹介します。
気になる質問があれば、ぜひチェックしてみてくださいね。
狭い土地に一戸建ては建てられる?
狭い土地に一戸建ては建てられます。
狭い土地に一戸建てを建てる場合、土地代や固定資産税の負担が小さくなるといったメリットがあります。
しかし、立地場所によっては規制の対象となる場合もあるため、事前の情報収集が重要となります。
また、住宅ローンの借入条件に土地の広さを挙げていることもあるため、住宅ローンを利用予定の方は、そちらも併せて確認しておけると安心です。
狭い土地は売れない?
狭い土地は売ることはできますが、なかなか買い手が付かない可能性も考えられます。
住宅にするにしても、デザインが限られてしまいます。
さらに、延べ床面積を広げるために3階建てにしたり、地下室を作ったりとしていると、建設費が嵩んでしまうといったデメリットがあります。
その他にも、隣家との距離が近く工事が大変など、一般的な広さの土地では気にする必要もない問題に直面するかもしれません。
そういった理由から、狭い土地を購入したいと考える人が少ないため、なかなか売れないのです。
しかし、狭い土地の売却に慣れている業者も存在します。
そういった仲介業者や買取業者をうまく活用して売るのも一つの手です。
田舎の土地を活用する方法
都市部であれば、狭い土地でも収益化が期待できます。
しかし、田舎であれば集客が期待できないため、駐車場経営や自動販売機の設置などで収入を得ることは難しいですよね。
そこで、田舎の土地を活用する方法の基本となるのが、集客に頼らないということです。
例えば、太陽光発電や資材置き場、トランクルーム設置などが挙げられます。
狭い土地の活用まとめ
以上、狭い土地の活用方法についてご紹介しました。
日本全国、様々な土地があります。
狭い土地は、活用方法が限られるというデメリットがあります。
しかし、上手く使えば収益を得ることも、快適に暮らすこともできます。
都市部にあることが多いため、使い方によっては大きな収益の期待もできます。
ぜひ、あなたにあった方法で、狭小地を活用してみてくださいね。