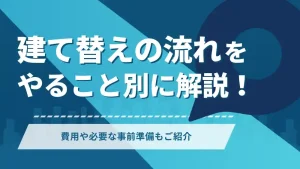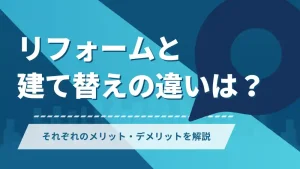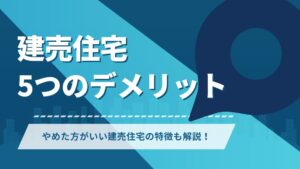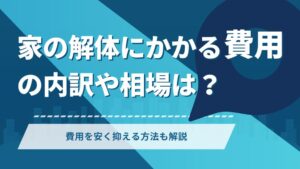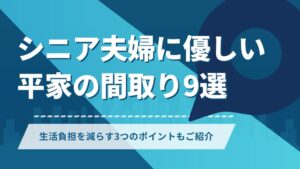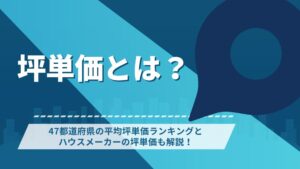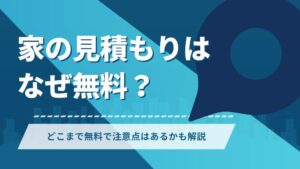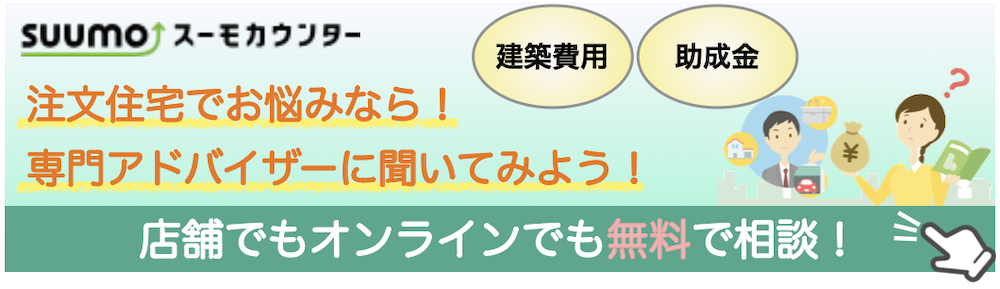
路線価とは?計算方法や路線価図の見方を解説
本ページはプロモーションが含まれています
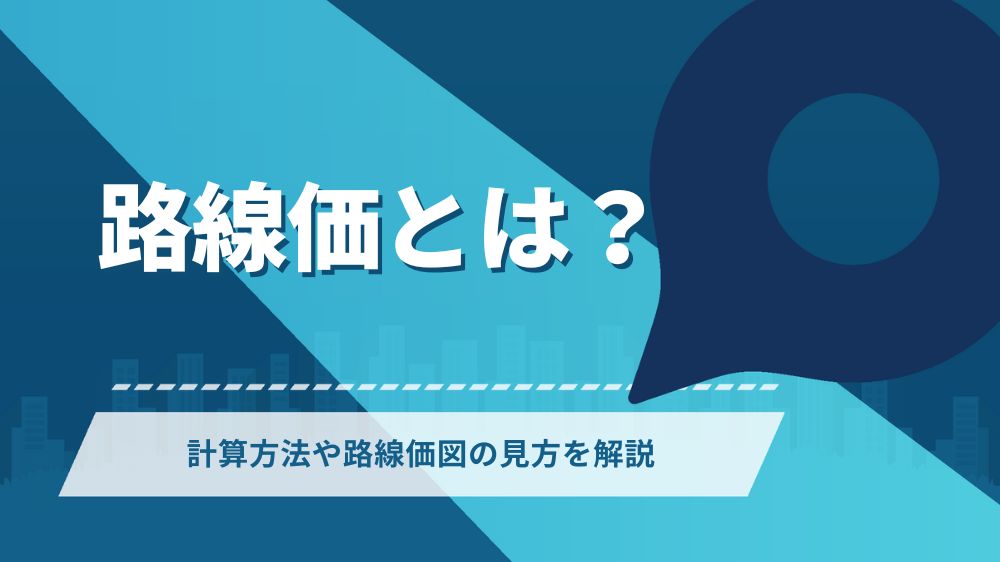
路線価と聞いてどんなものかピンとくる方は少ないのではないでしょうか?
「税金を調べたい」や「土地の資産価値が知りたい」という時に出会いがちな言葉になりますが、どのようなものなのでしょうか。
この記事では路線価の概要と実際の計算方法を解説いたしますので、路線価から不動産の価格を算出するための参考にしてみてください!
目次
路線価とは?知っておきたい公的な土地価格
路線価とは、「その年の1月1日時点での主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格」を国税庁が公表しているものになります。
主な使用目的は相続税や贈与税を計算するときに用いられます。
路線価と同様に覚えておきたい公的な土地価格についても解説します。
実勢価格(時価)
実勢価格とは、「不動産が市場で実際に売買された価格」のことです。
名の通り、実際の取引が成立する価格を指しているため不動産売却などを考えている方には大変参考になる情報になります。
実勢価格はいくつかの方法で調べることができるのですが、最も簡単に調べられる方法としては、国土交通省の土地総合情報システムを使用することで調べることができます。
公示価格
公示価格とは、「全国の標準値の土地価格」のことです。
国土交通省が毎年3月に、その年の1月1日時点のデータを公表しています。
国道交通省土地鑑定委員会が、土地を更地として評価をしている価格であり、一般取引での活用や相続税評価などに使用されます。
簡単にまとめると、更地の状態と仮定した土地のみの価値を示している価格のことになります。
調べたい場合は国土交通省の国土交通省地価公示・都道府県地価調査より調べることが可能です。
基準地標準価格
基準地標準価格とは、「各都道府県の標準値の土地価格」のことです。
各都道府県が毎年7月1日時点の評価データを公表しています。
評価方法は公示地価とほとんど同義であるため、国土交通省が出しているものが公示地価、都道府県が出しているものが基準値標準価格と覚えておきましょう。
内容自体もほとんど変わらず、調べる方法も公示地価と同様に国土交通省の国土交通省地価公示・都道府県地価調査にて調べることが可能です。
また、上記二つはそれぞれ公表されるタイミングが異なり、
- 公示地価:毎年3月(基準:1月1日)
- 基準値標準価格:毎年9月(基準:7月1日)
と、半年ほどの期間の違いがあるので、どちらが最新に近いかを判断した上で柔軟に見ていくのが良いでしょう。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、「固定資産税などの税額調査に用いられる基準価格」のことです。
名の通り、不動産の評価額を示したものになり、税率を掛け合わせることで支払うべき固定資産税額の算出が可能です。
簡易的な計算方法は下記になります。
固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
1.4%はあくまで標準税率のため、各都道府県や市区町村によって異なる場合もあり、都度確認をした上で計算するようにしましょう。
また、固定資産税評価額は公示地価の約70%になると言われているので、公示地価を参考にすることで概算の価格が算出できることも覚えておきましょう。
相続税評価額(路線価)
相続税評価額とは「相続税・贈与税を算出するときに用いられる基準価格」のことです。
評価方法は大きく分けて、路線価方式と倍率方式が用いられます。
路線価がある地域では路線価方式を採用し、計算方法は下記になります。
相続税評価額=路線価×奥行価格補正率×土地面積
路線価の調査方法は国道交通省が公表している路線価を用います。
国土交通省の路線価図・評価倍率表を用いることで、該当地域の路線価を知ることができます。
路線価図の見方
公的に用いられる土地価格の概要のつぎは、実際に路線価を調べるためにはどうすれば良いのかを解説していきます。
調査方法はわかったものの、専門家ではないので見方がわからないという方は多いのではないでしょうか。
ここでは、路線価図の見方を簡単に紹介します。
借地権割合に対応した記号
路線価図には借地権割合が示されています。

画像提供元/国土交通省
図面の右上にある数値部分が該当箇所になります。
アップをすると、このような表が描かれています。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
借地権割合は、相続税や贈与税を算出するときに用いる割合であり、もし親から子へ相続された場合に相続財産として評価に使用されます。
地区区分を表す記号
地区区分を表す記号もいくつか存在します。

画像提供元/国土交通省
中央上部に描かれている記号が該当するものになります。
それぞれがどのような地区に分類されているのかを示している図になります。
アップで見ると、それぞれ下記のような情報が記載されています。

画像提供元/国土交通省
実際の表で見ていくと、

画像提供元/国土交通省
・560C:普通商業・併用住宅地区
・620C:南側道路沿い繁華街地区
・660C:南側全地域繁華街地区
となります。
それぞれがどのような地区に該当するのかを確認できますね。
路線価を表す数字の表示
最後に路線価を表す数字についてです。

画像提供元/国土交通省
路線価図を見ていくと、「410D」や「430D」という数値が目に入ると思います。
この数字部分が、1㎡あたりの単価になります。
単位は千円となっており、「410」であれば1㎡あたり410,000円ということになります。
ちなみに数値のあとに記載されている「D」という記号が先ほど解説をした借地権割合になります。
路線価の計算シミュレーション
見方を解説してきましたが、方法論だけでは中々理解しきれない内容だと思いますので、実際にシミュレーションしてみましょう。
実際の手順に沿って解説をしていきます。
今回は路線価を求めるにあたり、
- 土地の一面が道路に面している宅地
- 土地の二面が道路に面する宅地
でシミュレーションしていきます。
土地の一面が道路に面する宅地|事例:福岡
- 対象地域:福岡県春日市
- 所有土地面積:96㎡
- 間口:8m
- 奥行:12m
▼全体図

画像提供元/国土交通省
▼対象地

画像提供元/国土交通省
該当箇所の路線価を調べます。
150Fの道路に面している100㎡の土地なので、路線価評価額算出の計算式としては
路線価=150,000円×1.0×96㎡
となり、14,400,000円となります。
土地の二面が道路に面する宅地(角地)|事例:大阪
- 対象地域:大阪府吹田氏
- 所有土地面積:240㎡
- 間口:10m
- 奥行:24m
▼全体図

画像提供元/国土交通省
▼対象地

画像提供元/国土交通省
該当箇所の路線価を調べます。
今回は角地で、165Dと170Dの道路に面している240㎡の土地なので、路線価評価額算出の計算式としては組み合わせが必要になります。
A:正面路線価×補正率
B:側面路線価×補正率×側面路線影響加算率
C:(A+B)×土地面積
これを計算していくと…
A:170,000円×1.0=170,000円
B:165,000円×0.97×0.03=4801円
C:(170,000円+4,801円)×240㎡=41,952,240円
という計算式で算出ができ、評価額は41,952,240円となります。
路線価に関するニュース
続いて、路線価に関する直近のニュースを見ておきましょう。
毎年更新されるので、傾向を掴むためにも毎年抑えておく方が良いでしょう。
路線価は令和4年・5年と2年連続で上昇している
路線価は令和4年、5年と上昇トレンドになっています。
2023年7月3日に国税庁が公開した路線価では、全国32万地点の標準宅地の平均が2022年から2023年にかけて1.5%上昇しました。
2022年から2023年にかけて標準宅地の前年比変動率の平均値が最も上がったのは、北海道で6.8%。
関東の主要都市では、東京:3.2%、埼玉:1.6%、千葉:2.4%、神奈川:2.0%と軒並み上昇する結果に。
郊外で上昇している傾向も見られるため、テレワークの普及による影響があると思われます。
大阪や京都など関西の路線価も上昇している
関西でも関東と同様に路線価が上昇しています。
大阪:1.4%、京都:1.3%と上昇している傾向に。
この路線価の上昇はアフターコロナを見据えた商業地域の賑わいが影響していると考えられます。
またインバウンド需要を狙ったホテルなどへの投資も相次いでおり、その影響で主要都市での路線価が上昇しているのではないでしょうか。
路線価に関するよくある質問
路線価に関してよくいただく質問をまとめています。
路線価と聞いてもやはり定義がわかりづらいので、ここで明らかにしていきましょう。
- 調査方法
- 単位
- 公示地価との違い
上記3つを解説します。
路線価はどうやって調べられる?
路線価は国土交通省の路線価図・評価倍率表を用いることで調査することが可能です。
該当地域名から索引し、実際の箇所の路線価を確かめることができます。
過去に遡って調べることができるため、今までの路線価推移が知りたい方も同様の方法で調べることが可能です。
路線価の単位は?
路線価の単位は「千円」になります。
路線価図を確認すると「170D」や「80F」のような「数字+記号」が書かれています。
その数字部分が1㎡あたりの金額になります。
例えば100㎡の土地を所有していた場合、「170D」と記載されていれば、1㎡あたり170,000円なので、ここに面積と奥行補正率を掛け合わせてあげることで評価額を算出することが可能です。
路線価と公示価格の違いは?
路線価と公示地価の違いも気になると思いますので、表にまとめます。
簡単にまとめると、
- 路線価:路線(道路)に面した土地の評価額
- 公示地価:土地を基準とした土地の標準額
となります。
それぞれ意味合いが異なりますので、覚えておきましょう。
| 路線価 | 公示地価 | |
|---|---|---|
| 調査期間 | 国税庁 | 国土交通省(土地鑑定委員会) |
| 価格の決め方 | 2人以上の不動産鑑定士が鑑定 | 公示地価などを参照し評価、決定 |
| 評価時期 | 1月1日時点 | 1月1日時点 |
| 発表時期 | 3月中旬 | 7月1日 |
| 調査地点 | 「標準地」1㎡ | 「路線に面する土地」1㎡ |
路線価まとめ
路線価について詳しく見てきましたがいかがだったでしょうか。
特に路線価図の見方や計算方法を身につけておけば、相続などの時の税金の計算に使用できるだけでなく、自身が所有している土地を売却したい時にも簡易査定をすることができます。
公表タイミングでは、ニュースでトピックが報道されるためトレンドを抑えておくと良いと思います。